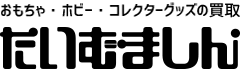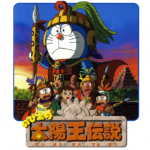『映画ドラえもん』の歴史をたどる【第6回】19作目『南海大冒険』~20作目『宇宙漂流記』
『映画ドラえもん』シリーズ19作目『のび太の南海大冒険』(1998年)は、藤子・F・不二雄先生がまったくタッチしないかたちで制作される初めての映画となった。
私の中で、藤子F先生の不在はあまりにも大きな事態だった。長らく頭から拭い去ることはできなかった。F先生がこの世界にいない、という事実が頭をよぎれば、どうしようもなくやるせない気持ちがわいてきた。『のび太の南海大冒険』は、そんな精神状態がまだ収まりきらないうちに公開を迎えた作品だった。
藤子F先生が不在の世界で初めて公開された『映画ドラえもん』は、『のび太の南海大冒険』ではなく、1997年に公開された18作目『のび太のねじ巻き都市冒険記』だった。
しかし、『ねじ巻き都市冒険記』の構想は藤子F先生ご自身によるものだし、原作マンガの途中までは実際に藤子F先生が描いていた。『ねじ巻き都市冒険記』は、いわば藤子F先生の遺作であって、この作品までは先生が直接かかわっていたといえる。
だから、『のび太の南海大冒険』こそが、藤子F先生ご不在の世界で初めて一から制作され公開された映画なのだった。少なくとも私の主観の中では、『ねじ巻き都市冒険記』と『南海大冒険』の間にくっきりとした区切りの線が引かれている。
『のび太の南海大冒険』を劇場公開時にリアルタイムで観た私は、正直なところ気持ちがノラなかった。「F先生がいないとこんなにも変わってしまうんだ……」と少なからずショックを受けた。客観的に見て本当に変わってしまった部分もあっただろうし、それ以上に、私の頭の中にこびりついた「F先生はもういない」という意識が強力なバイアスとなって「F先生がいないとこんなにも変わってしまうんだ……」という観念にとらわれた面も否定できない。
それほどまでに、あのころは藤子F先生の不在という事実が私の精神に大きな影を落としていたのだ。
『のび太の南海大冒険』パンフレット
ここで、私の“ファンとしてのありよう”をあえてクリアカットに分類し、示そうと思う。
ファンとしてのありようというのは、すなわち心のありようのことだ。そんな自分の心模様をわざわざ分類して「私はこういうファンなのだ!」と断言してしまうことに、いささか無理や抵抗を感じないでもない。けれど、『南海大冒険』を観たときの私の心情を語るには、私のファンとしてのありようがどうしてもかかわってくるので、あえて分類してみるのだ。
私は、マンガファンやアニメファンや映画ファンやドラえもんファンというよりも、まず根本的には藤子先生のファンである。藤子先生が描いた作品と藤子先生ご本人が好きで好きで好きでたまらないのだ。
私は、マンガというジャンルを強く愛しているし、アニメや映画にも好きな作品が多々あって、さらに熱心なドラえもんのファンだとも自覚している。自分はマンガ愛好者であり、アニメや映画が好きだし、ドラえもんファンだと言ってしまえる。しかし、あえて自分の愛情のありようを分類し線引きして最も的確な言い方に絞るとするならば、まずは「藤子ファン」なのである。
藤子先生ご自身が直接描いた作品が好きだし、藤子先生が歩んできた歴史が好きだし、藤子先生が発した言葉が好きだし、藤子先生ご本人が好きだ。「原作至上主義者」とか「原作厨」なんて言葉があって、私はそういう表現をあまり好まないし、そういう呼ばれ方をしたくもないが、でも言ってしまえば、藤子ファンとしての私は原作至上主義的であり原作厨のような存在なのだろう。
藤子先生が直接描いた作品こそが圧倒的にして最高で最大の愛好対象なのである。
けれど、そのうえで私は、藤子先生が描いたマンガから派生したアニメ作品や映画やドラマやグッズや諸々の企画など二次的な事象にもなるべく受容的であろうとしてきた。「原作の魅力を痒いところに手が届くかのごとく見事に再現してくれている!」と心から感じられるアニメやグッズを愛好するのはもちろん、原作のテイストからだいぶ離れているなあ……と思えるものであっても「面白ければOK」みたいな気持ちで、広く愛好の対象としてきた。
藤子先生が描いた原作マンガから派生し拡散していく藤子ワールドを、なるべく否定しない。できるだけ非難しない。なるたけ包摂する。私は10代のころから「寛容」の精神を重んじる藤子ファンだった。
「なるべく」「できるだけ」「なるたけ」などと、わざわざそんな副詞を添えたのは、「絶対に〇〇しない」と厳格な自己ルールを課してしまうとそのうち窮屈さに襲われイヤになってくるし、自分を束縛するものなど外界にあふれているのにわざわざ自分を縛りつける必要はないだろう、という思いがあるからだ。「絶対に」ではなく「なるべく」というのが私のモットーである。
というわけで、今述べてきたことを簡潔にまとめれば、
藤子先生ご本人が描いた作品を至高のものと感じるけれど、原作から派生した二次的事象も極力否定しないでなるべく楽しみたい、というのが中高生のころから続く私の藤子ファンとしての基本的スタンスである。
そんなスタンスの持ち主だから、藤子F先生が直接携わっていない『のび太の南海大冒険』であっても、それを理由に楽しめないなんてことはないはずだった。
ないはずだったのに、実際にはノレなかった。F先生がいらっしゃらないとこんなふうになるのか!とショックを受け、切なくなってしまった。
映画の出来が客観的にどうこうという以前に、F先生死去の事実がそれほど私の精神に大きく作用していた、ということなのだろう。
1996年9月23日以前と以後の世界に、深い分断を感じざるをえなかった。
『のび太の宇宙漂流記』パンフレット
正直なところ、その翌年(1999年)に公開されたシリーズ20作目『のび太の宇宙漂流記』にもノレなかった。
2年連続でノレないとなると、これはもう、自分にとって一大事だ。ずっと自分事のように近しく思えていた『映画ドラえもん』が他人事のようによそよそしく感じられる日が来るなんて……。
前作の『南海大冒険』の配給収入は、それまで公開された『映画ドラえもん』シリーズのどの作品をも上回っていた。『映画ドラえもん』は時代を経ても多くの人に観られ、愛されている。私が『映画ドラえもん』を他人事のように感じたのは、誰のせいでもなく私の心持ちのせいだ。誰かが間違っているわけでも、何かが悪いわけでもない。私の心がついていけなくなったのだ。
私は翌年以降も『映画ドラえもん』を劇場で観続けるだろう。それは私にとって欠かせない、年に一度巡りくる季節的な習慣であり風物詩であり一種のお祭りだ。しかし、今後は「自分が楽しめなくても、みんなが楽しめる作品であればよい」という、ちょっと引いた目線で祭りに参加することになるのだろう……。
そんなふうに、なかば達観したかのようなあきらめ気分が胸のうちに生じた。
(このころは、大長編の『映画ドラえもん』よりも、同時上映作の『帰ってきたドラえもん』(1998年)や『のび太の結婚前夜』(1999年)といった感動シリーズのほうに心が傾斜していたような記憶もある)
劇場公開時はそのように感じてしまった『南海大冒険』と『宇宙漂流記』ではあるものの、あれからずいぶん月日が流れた。今なら、もう少しフラットに、もう少し精神的余裕をもって、もう少しバイアスから自由になって鑑賞できるのではないか。そう考えて、この機会に2作品を観返してみた。
『のび太の南海大冒険』特別割引券
『のび太の南海大冒険』は、てんとう虫コミックス『ドラえもん』45巻に収録された短編「南海の大冒険」のエピソードをアレンジしてストーリーの冒頭に配置している。
そうやってストーリーの冒頭に短編『ドラえもん』のエピソードを使い、それを発端に壮大な長編作品へと話を膨らませていく手法は、シリーズ第1作『のび太の恐竜』のやり方に近いものがある。
『のび太の恐竜』のときは原作者である藤子F先生がそれをやったわけだが、『のび太の南海大冒険』では、藤子F先生亡きあとの映画づくりの手法としてそれが選択されたのだ。
短編の「南海の大冒険」は、ロバート・ルイス・スティーヴンソンの海洋冒険小説『宝島』をモチーフとしている。のび太が『宝島』を読んで触発され、宝探しに出かけるのだ。それゆえ、「南海の大冒険」のエピソードをもとに話を膨らませた映画『のび太の南海大冒険』でも、必然的に宝探しが描かれることになる。
この映画における冒険のメイン舞台は、宝島なのだ。
物語の途中から宝探しが冒険の主眼ではなくなっていく傾向はあるものの、ラストでちゃんと宝物の獲得シーンが描かれたりして、宝探しの要素は最後まで忘れられていない。
ロバート・ルイス・スティーヴンソンの『宝島』
宝探しということについて、藤子F先生はこんなことを述べていた。
「誰にでも好みの題材、好みの世界って物はありますがね。例えば僕の場合、何かと言えば恐竜を登場させるなんてのもそれですね。アイディアに困ると宝探しを始めたりね。「オバQ」「パーマン」「ウメ星デンカ」皆やりましたね。「ドラえもん」に至っては、もう十回ぐらい宝を探してるんじゃないかな」(藤子不二雄ファンクラブ会誌「月刊UTOPIA」第7号、1983年)
藤子F先生が本格的に漫画家を志すようになった大きなきっかけが、手塚治虫先生の『新寶島』(1947年)を読んだことだった。そして、上掲の藤子F先生のコメントのとおり“宝探し”は先生が何度も描いてきたお気に入りの題材だった。この2点に加え、先述したように本作がシリーズ第1作『のび太の恐竜』と同じく原作の既存の短編エピソードを膨らませて長編化する手法を採っている点を踏まえれば、『のび太の南海大冒険』は、藤子F先生と『映画ドラえもん』の原点をあらためて見つめようとした作品であった、と受けとめることができそうだ。
藤子F先生が描いた大長編の原作マンガが存在しないうえ、先生がノータッチの状態でつくられた映画ではあるものの、藤子F先生の根っこのほうへ眼差しを注いでいた作品だったのだ……と思えば、そう思えないこともないのが『のび太の南海大冒険』なのである。
この映画の序盤パートは、すでに述べてきたように、藤子F先生が描いた『ドラえもん』の短編マンガ(つまり、大長編ではない通常の『ドラえもん』)から「南海の大冒険」のエピソードを採用している。その序盤パートに “ほどほど嵐”というひみつ道具が登場する。船遊びを面白くするため嵐を起こす道具である。
この道具で引き起こされる嵐はあくまでもほどほどの嵐だから、嵐に襲われるスリルは味わえるけれど、船は沈まない。安全にスリルを満喫できる道具なのだ。
その後まもなくして、“ほどほど大砲”のシーンも見られる。撃っても当たらない安全な大砲である。はずだったのに、この大砲に備えられた“ほどほど装置”が故障してしまっていて、ほどほどでは済まなくなった。
そんなふうにトラブってしまったけれど、私はこの“ほどほど嵐”“ほどほど大砲”“ほどほど装置”に無性に心誘われるものを感じた。 「ほどほど」という、ちょうどよい加減を示す語をひみつ道具の名前とその道具の装備に入れ込んでいるのがツボなのだ。
藤子F先生の、ちょうどよい加減を表現する絶妙なバランス感覚にはよく唸らされるが、この「ほどほど」の語を使ったネーミングも、私が思う“藤子F先生らしさ”の旨味をほどよく授けてくれる。
「南海の大冒険」を収録したてんとう虫コミックス『ドラえもん』45巻
そんな「南海の大冒険」のエピソードを使用した序盤パートに、原作の「南海の大冒険」にはない映画オリジナルの肉付けがほどこされている。のび太らが「海」をテーマに夏休みのグループ研究をしている、という要素が加えられたのだ。
しずかちゃんが「海中の植物」について調べ、スネ夫が「海の生物の進化」を調べる……といったふうに、自由研究にふさわしいまっとうな研究テーマが紹介された直後、ジャイアンが「どんな魚がうまいか調べる」と宣言したときは、ちょっと笑ってしまった。
その後、ジャイアンがスネ夫に「やっぱり今んところ海の魚じゃサンマがいちばん、そんでもってカマボコが2番ってところだな」と自由研究の途中経過を報告するくだりがある。ジャイアンのその豪快な天然ボケを、スネ夫が華麗にスルーして別の話題を差し出すところが妙におかしかった。
『のび太の南海大冒険』は、何度も言うように短編原作「南海の大冒険」のエピソードを物語の序盤パートに使っている。そのパートに続き、てんとう虫コミックス『ドラえもん』41巻に収録されている「無人島の大怪物」のエピソードも少しだけ使って、そこからいよいよ映画オリジナルの冒険ストーリーへと展開していく。
のび太たちは、時空間の乱れによって17世紀のカリブ海へタイムスリップし、本物の海賊と出会う。そして、カリブ海に浮かぶトモス島へ上陸。その島が本作の冒険の主舞台となる。
のび太たちが夏休みのグループ研究で海について調べている流れで、カリブ海の船上でも海に関する学びが行なわれる。日常の世界から離れて冒険に旅立ったというのに、夏休みの宿題がこんなところでもついてまわるのだ。ドラえもんいわく「退屈しのぎに海のお勉強をしましょう」とのことだった。
そこで海の何を勉強したのかと言えば、海にまつわる伝説の魔物や怪獣についてであった。“伝説復元機”が生みだすバーチャル映像で、人魚、大海蛇、ポセイドンなどが順々にのび太らの眼前に出現していった。
このグループ研究において、しずかちゃんは海中の植物、スネ夫は海の生物の進化というふうに理科的な調べ物をし、ジャイアンはどの魚がうまいかという個人的な欲求最優先の調査(科目でいえば家庭科にあたるのだろうか、それとも理科だろうか)を実践したわけだが、ではのび太は何をしたのかと言えば、スティーヴンソンの『宝島』に夢中になっていた。それは、言ってみれば文学への関心であった。
理科×2、家庭科(?)、文学……。それらの科目のうえに、ついには伝説の魔物や怪獣といった民俗学的な分野まで加わって、のび太たちのグループ研究は、海という統一的なテーマを軸に学問分野をいくつもまたぐものになっていった。
そして、ここで海にまつわる伝説上の魔物や怪獣に言及したことが、ストーリー上の巧みな伏線にもなっている。のちに明らかになる敵の悪事(改造動物をつくって売る)にがっちり結びついていくのだ。
『のび太の南海大冒険』劇場用グッズいろいろ
芝山努監督は、この作品でジャイアンを主役にしてやろうと試みた、と述べている。その発言のとおり、ジャイアンがずいぶんとドラマをつくっている。
特に、海賊船の乗組員の少女・ベティとジャイアンの淡いラブロマンスは見どころだろう。淡いラブロマンス、という表現は芝山監督によるものだが、本作では、ベティとジャイアンの関係性、2人の意気投合ぶりを描写することに力点が置かれている。
2人の波長の合い方は、尋常ではない。なんとベティは、ジャイアンのあの破壊的・公害的な歌声を「素敵だねえ」と心から誉めてくれるのだ。ラストの別れぎわには、ベティがジャイアンを海賊の一員にスカウトする一幕もあり、そこでも「また歌を聴きたかった」とジャイアンの歌への惚れこみっぷりを見せつけてくれた。ジャイアンの歌を聴いたことのあるあらゆる人物の中で、ベティは最高最良最強のファンではなかろうか。奇特なファンだとも思うけれど。
この映画におけるジャイアンの存在感の強さは、次のようなところでも見られた。乗っていた船から海に落ちたのび太の手を、ジャイアンが握って助けようとするシーンがある。助けようとしたものの、海流の勢いに負けたジャイアンは、のび太の手を離してしまう。遠くへ流されていくのび太。不可抗力だったとはいえ、ジャイアンはそのことを非常に悔やんだ。
その思いが強いから、ベティが川の急流に落ちたときは握った手を離さなかった。絶対に離さなかった。
そうしたシーンに、ジャイアンの心理がよく表れており、彼の存在感が発揮されている。
そのあと、落下しそうなドラえもんの手をのび太がつかんで2人とも落ちていく、というシーンが見られる。このシーンは、のび太の手を握って離してしまったジャイアン、ベティの手を握って離さなかったジャイアンとイメージの重なるところがある。下方へ落ちていく友の手を握って助けようとするシーンとして、3箇所がオーバーラップするのだ。
ドラえもんが途中で四次元ポケットを紛失し、使えるひみつ道具がごく限られてしまう、というのもこの映画の持ち味である。それまでに公開された『映画ドラえもん』でも、一時的にひみつ道具の使用が封じられることで物語が展開していくことはあったが、本作は一度失った四次元ポケットが物語のラストまで戻ってこないという、異例の事態となっている。ドラえもんの腹に四次元ポケットがない状態が、そうとう長いあいだ続くのだ。
腹のあたりが寂しくなったドラえもんがその腹に自らポケットの絵を描くシーンまであって、なんだかいじらしかった。
『のび太の南海大冒険』入場者プレゼント「ミニドラりん丸」
本職の声優さんではない芸能人が多く声優として参加しているのも『南海大冒険』の特徴だ。それまでの『映画ドラえもん』と比べて、これは実に顕著な変化だった。
OPとEDの歌い手はタレントの吉川ひなのさんだった。おなじみの「ドラえもんのうた」が吉川さんの無邪気そうな舌足らずの歌声によって、だいぶ違う歌に聞こえた。EDの「ホットミルク」では曲の合間に吉川さんのモノローグが挿入されて、けっこう面食らった。『映画ドラえもん』のEDとして何か底が抜けた気がしたし、ある意味革新的だとも感じた。
今回あらためて『のび太の南海大冒険』を観て、1998年当時の私はなぜこの映画を観てあんなにもショックを受けたのだろう、と不思議に思えてきた面もあれば、当時の私の気持ちが今となってもよくわかると感じられる面もあった。
あれから22年がすぎた今、少なくともこの映画を観返してショックを受けるようなことはなかった。むしろ、意外に楽しく観られた、というのが素直な感想である。楽しく観られるに越したことはないから、まあ、よかったのではないだろうか。
『のび太の宇宙漂流記』特別割引券
続いて、『のび太の宇宙漂流記』もずいぶん久しぶりに観た。たぶん、公開時に劇場で観て以来の鑑賞になったはずだ。
『のび太の宇宙漂流記』が公開された1999年には、映画『スター・ウォーズ』新三部作の1作目『ファントム・メナス』の公開が控えていた。この年に公開された『映画ドラえもん』が宇宙を舞台とする作品になった背景には、そうしたタイミングも関係していたのではないか。
『スター・ウォーズ』と言えば、これはもう藤子F先生が大好きな映画だ。先生の描くマンガの中でたびたびパロディのネタにされている。それを思えば、多少なりとも『スター・ウォーズ』に影響されて『映画ドラえもん』の新作が制作されたことに対して、一種の藤子Fスピリットを見いだすこともできるだろう。
『スター・ウォーズ』が紹介されるとき、この映画は“スペース・オペラ”である、とジャンル分けされることが多い。藤子F先生ご存命時の『映画ドラえもん』で宇宙を舞台にした事例を挙げれば、『のび太の宇宙開拓史』『のび太の宇宙小戦争』『のび太と銀河超特急』などが思いあたるが、それらの作品と比べても“スペース・オペラ”といって最もしっくり来るのが、この『のび太の宇宙漂流記』である。
スペース・オペラとは、SF作家・横田順彌氏の言葉を借りれば「西部劇映画がホース・オペラと呼ばれたのと同趣向の用法」で「舞台を大宇宙におき、ハンサムなヒーロー、絶世の美女たちが、馬の代わりにロケットやタイムマシンを駆って、光線銃片手に宇宙海賊やモンスターと戦う、夢と冒険の奇想天外な物語」のことである。
『のび太の宇宙漂流記』劇場用グッズの下敷き
『のび太の宇宙漂流記』の劇中においてのび太たちいつものメンバーが友情を交わすゲストキャラクターは、4人組だった。リアンというリーダー格の少年をはじめ、一輪車型ロボットのログ、妖精のような小人少女フレイヤ、巨体の岩石型人間ゴロゴロの4人である。
その4人が乗る宇宙船内で、のび太たちとの出会いがあった。
リアンらは、特定の星に定住していない。リアンの祖先は300年前に母星を捨てた。発達しすぎた物質文明が環境破壊を進め、自然の体系を乱して植物は枯れ果て、呼吸装置なしでは出歩けない死の星になってしまったからである。
そこでリアンの祖先は、緑あふれる理想の星を求めて宇宙へ旅立った。やがて、同じような境遇の他の種族たちも合流して「銀河漂流船団」を形成。300年ものあいだ宇宙を漂流しながら理想の星を探し続けている。
リアンら4人は、漂流を続ける宇宙船内で生まれた新世代であり、その新世代たちによって結成された「宇宙少年騎士団」のメンバーである。宇宙少年騎士団は、自分たちが住めそうな星を探し、調査をおこなっている。
そんなリアンら4人とのび太ら5人が、リアンらが操縦する宇宙船内で出会うのである。
のび太たちがリアンたちと出会ったとき、宇宙船のワープ装置が壊れてしまっていた。そのため、地球へ戻るには1億800万年もかかるという。
『のび太の宇宙漂流記』では、そんなはるか遠い宇宙空間で冒険が繰り広げられるのだ。
そんなふうにリアンらの境遇やのび太らと出会った場所をざっと見ていくだけでも、この映画が壮大な宇宙を舞台したスペース・オペラだと認められる。
そうしたキャラクター設定や舞台設定に加え、奇怪な星々での冒険、敵との戦いといった活劇が繰り広げられ、本作はスペース・オペラらしさを色濃くまとっていくのだった。
THIS IS ANIMATION『映画ドラえもん のび太の宇宙漂流記』「Making Book」と「FILM STORY BOOK」
『のび太の宇宙漂流記』の主舞台は、宇宙空間の中でもとりわけ宇宙船である。地球上から宇宙へ場面が移って以降、いくつかの未知の星に降り立つ以外は、宇宙空間を航行する宇宙船が主な舞台なのである。それゆえ、作中におけるいくつかの宇宙船の存在感はかなりのものだ。
宇宙船の存在感をいっそう強くしているのが、メカのデザインを担当したスタジオぬえの宮武一貴氏である。宮武氏がデザインした宇宙船は、それまでの『映画ドラえもん』で目撃してきた光景とは少し異質の、鮮烈なデザイン美を感じさせた。
宮武氏が自分で手がけたメカデザインの最初の記憶は、小学3年生のころまでさかのぼるという。『海の王子』のはやぶさ号を「僕ならこうする」と勝手に形をなおしたりしたのだそうだ。
『海の王子』と言えば、藤子不二雄先生が「週刊少年サンデー」の創刊号(1959年)から連載開始した海洋冒険SFマンガである。“藤子不二雄初のヒット作”と呼ばれることもあるこの作品が、宮武氏のメカデザイン歴のルーツにあるのだ。
そんな宮武氏が、自身のルーツからおよそ40年の時を経て『映画ドラえもん』のメカデザインを手がけることになったのだから、さぞかし感慨深かったことだろう。この仕事を依頼されたときのことを振り返って、藤子先生の作品に恩返ししなくちゃいけないと思っていたので大喜びで引き受けた、と述べている。
宮武氏が『のび太の宇宙漂流記』のためにデザインしたメカたちは、氏のメカデザイン歴の根っこである『海の王子』へ思いを馳せるかのごとく、海の生き物をモデルにしたものばかりになった。
その逸話を知った私は、自然と藤子ファン心をくすぐられたのだった。
藤子・F・不二雄大全集『海の王子』全3巻
『のび太の宇宙漂流記』は、遠い、遠い、あまりに遠い壮大な宇宙を舞台にした作品だが、物語の始まりに関しては、定石どおりのび太らが暮らすいつもの家、いつもの町が舞台となっている。
とはいえ、そんないつも風景を描いた物語のスタート時点から、すでに宇宙を見せまくっている感はあった。なにしろ、バーチャル宇宙空間のシーンから物語が始まるのだから。
未来の宇宙アドベンチャーゲームである“スタークラッシュゲーム”がつくりだした、本物そっくりの宇宙空間。のび太らいつものメンバーがその空間でゲームをプレイするシーンから、この映画は幕を開けるのだ。
そのように発端から宇宙を意識させるシーンがあって、そこを経て、のび太らは本物の宇宙へ出ていくことになる。
『映画ドラえもん』(だけでなく多くの藤子F作品)の魅力のひとつに、日常の中に入り込んだ非日常、あるいは、非日常の中に挟み込まれる日常という要素がある。日常と非日常の対比やバランスから、絶妙な面白味を生み出しているのだ。
その意味では、『のび太の宇宙漂流記』は非日常と日常のうち日常の感覚のほうを味わえる余地が少なめの作品だった。少なくとも私は、そういう印象をおぼえた。私がこの映画から藤子Fらしさの欠乏を感じた理由の一端は、そこにあったのかもしれない。
そうではあるものの、この映画を観て“日常に入り込んだ非日常”の感覚を魅力的に味わえるシーンがあるにはあった。
序盤で描かれた、のび太の部屋が無重力化するシーンだ。
私は以前から、“おざしきつりぼり”や“おざしきゲレンデ”など「おざしき」の冠がついたひみつ道具に特有の愛着をおぼえている。本来なら屋外で展開される大規模な事象が日常生活を送るいつもの部屋の中でこぢんまりと実現する、その匙加減がなんとも好ましいのだ。
それゆえ、この映画に登場する“おざしき宇宙船”にも、同じような好ましさを感じた。
“おざしき宇宙船”によって、のび太の部屋が宇宙船内と同様の無重力空間になる。その空間を、のび太やしずかちゃんが宙に浮かんで遊泳する。部屋に置いてある品々もいっぱい宙に浮き、特に飲みかけのジュースがシャボン玉のごとく浮遊する光景に目を引かれた。
このシーンは、のび太の部屋といういつもの日常に、宇宙船内の無重力状態という非日常が入り込んで、日常と非日常のブレンド感覚を少し不思議な味わいで楽しく授けてくれる。
『のび太の宇宙漂流記』入場者プレゼント「ミニドラシャトル」
今回観返してみて、『宇宙漂流記』も思いのほか楽しめた。『南海大冒険』もそうだったように、当時劇場で観たとき気分がノラなかったことが不思議に感じられるほどだ。
と同時に、私が藤子F先生ご存命時の『映画ドラえもん』から感じ取っていた魅惑的な藤子Fテイストからの遊離具合をあらためて強く感じざるをえず、当時の私の心境では受けつけがたいところのある作品だった、ということも再確認できた。
劇場公開当時はあまり気持ちがノラなかった『南海大冒険』と『宇宙漂流記』だが、今思えば、藤子F先生亡きあとも『映画ドラえもん』を持続させようというチャレンジは並大抵のプレッシャーではすまなかっただろう。おびただしいエネルギーが必要だったことだろう。藤子F先生の遺志を継ごう、よい映画をつくり続けよう、これからも多くの人たちに楽しんでもらおう、と努めてくださった方々に、今さらながら感謝したい。
キネ旬ムック『20周年だよ!ドラえもん ザ・ムービー』
(『のび太の宇宙漂流記』は「ドラえもん映画TV20周年記念作品」として公開された。このムック本は『宇宙漂流記』公開日の少し前に発売された)
《第7回へ続く》
『モッコロくん』を読んで藤子マンガに惹かれ、小学校の卒業文集には「ドラえもんは永遠に不滅だ!」と書きました。
中学で熱狂的な藤子ファンになり、今でもまだ熱烈な藤子ファンです。

記事一覧はこちら