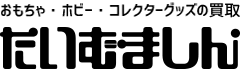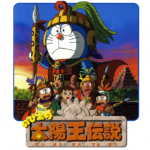『映画ドラえもん』の歴史をたどる【第5回】 ~18作目『ねじ巻き都市冒険記』~
1997年に公開されたシリーズ18作目 『のび太のねじ巻き都市(シティー)冒険記』は、私の中で藤子・F・不二雄先生死去の記憶と直結している。そのときの悲しみがあまりにも大きく、劇場でこの映画を観てどう感じたか…という記憶が曖昧である。
悲しみは日常生活の中でしだいに心の底へ隠れていったが、藤子F先生の遺作となった『ねじ巻き都市冒険記』の映画を眼前で観てしまうと、その内容にすんなり没入するのは難しかった。まだそこまでは感情が安定していなかった。それでも、劇場へ足を運んで映画を観る気力だけはあったようだ。
現在もやはり藤子F先生の遺作として強く心に刻まれており、あれから何年経ってもそのイメージから完全に脱することはできない。
藤子F先生は、「月刊コロコロコミック」1996年9月号から連載を開始した『大長編ドラえもん のび太のねじ巻き都市冒険記』の執筆途中で倒れられ、帰らぬ人となった。1996年9月23日のことだった。
当日の夜のニュース番組で訃報に触れた私は衝撃を受け、悲しみに襲われた。日頃はひからびた生活をおくっている私がまだこんなにも泣けるのか……と思えるくらい泣けた。
「月刊コロコロコミック」で『ねじ巻き都市冒険記』の連載第1回を読んだとき、藤子F先生がほとんどペン入れをされていないように見えた。別の人がすべてのキャラクターを描いているようだった。(あとで知ったことだが、藤子F先生のペンが入っているのは冒頭のカラー4ページのみだった)。先生の体調の悪さがまざまざと伝わってくるようで愕然としたおぼえがある。それでも、先生の他界がすぐ先に迫っているとは考えられなかった。ぜんぜん覚悟なんてできていなかった。
だが、その日が来てしまった……。
『ねじ巻き都市冒険記』で藤子F先生が直接手がけたのは、連載3回目の下絵ラフまでだった。それ以降の第4回〜6回のお話づくり、作画などは、残された者たちの仕事となった。当時藤子F先生のチーフアシスタントで『ねじ巻き都市冒険記』のペン入れをすでに任されていた萩原伸一氏(現・むぎわらしんたろう先生)が4回目以降も執筆することになった。
藤子F先生が書きとめていたアイデアノートや先生が生前に関係者へ伝えていた話などを手がかりに、萩原氏、芝山努監督、小学館の担当氏らが打ち合わせを重ねてアイデアを拾い上げ、難解なジグソーパズルのピースを埋めるように物語を組み立てていった。
藤子F先生が構想していたこと、描こうと思っていたことを推理し、探りあて、想像し、構築していくプロセスは、たいへんな難しさや重圧があったと思う。そんな難業に挑んでくださった方々のおかげで、『ねじ巻き都市冒険記』の原作マンガは無事完結に至り、映画も予定どおり公開された。
とはいえ、先生が亡くなって半年も経たない時期に公開された映画とあって、私には、作品の内容がどうだったかよりも「先生はもういないのだ……」という厳然たる事実のほうが圧倒的に重くのしかかってきた。映画の内容にのめり込んでいけないというか、映画を観た記憶の上に藤子F先生死去の悲しみがかぶさってくるというか……。
そんな思いにかられた作品ではあるものの、ここであらためて映画『のび太のねじ巻き都市冒険記』の内容それ自体に思いをめぐらせたい。そのさい、劇場で初めて観たときのおぼろげな記憶と、その後ビデオなどで観返したときの印象と、このたびまた鑑賞して抱いた感想とが入り混じった記述になることをお断りしておく。
パンフレット
『ねじ巻き都市冒険記』の冒険の舞台は、ひとつの小惑星だった。ドラえもんは22世紀の商店街で福引きをするが、ぜんぶ外れ券ばかりという結果に。外れ券は小惑星引換券だった。小惑星がもらえるならぜんぜん外れではないではないか……とも思えるが、じっさい外れなのである。
なぜなら、そこでもらえる小惑星というのは、火星と木星の間に無数にちらばっている星クズの中でも特に使いようのないクズの中のクズだからである。
それでも一応念のため、もらえることになった小惑星をのび太がひとつひとつ確かめに行くと、やはりどの星も使いものにならなかった。
と思っていたら、最後に確認した小惑星が緑豊かな美しい星でびっくり。その星に、のび太たちは“ねじ巻き都市(シティー)”を建造することになった。
ねじ巻き都市には、各人が持ち寄ったぬいぐるみなどを住まわせた。そのぬいぐるみたちは、ドラえもんが出したひみつ道具“生命(いのち)のねじ”で生命を吹き込まれて自ら動くことができる。
生命のねじを使うと、ぬいぐるみや人形などの玩具が生きて動けるようになるのだ。ただ動けるのではなく、「生きて」というのが肝だ。
生命のねじのおかげで動きだしたぬいぐるみを見たジャイアンが「生きてるみたいだ」と感嘆すると、ドラえもんが「ほんとに生きてるんだよ」とこともなげに答えるくだりがある。その、ごく短いやりとりに私は震えた。
無生物が生命体になるのである。命を宿すのである。ぬいぐるみや人形が自律的なロボットと化して動きだすのではなく、生命を持った生き物となって活動するのである。
そのことから、
「この作品は、生命の秘密にかかわる何ごとかに迫ろうとしているのではないか」
「生命をめぐる重要な問いを投げかけてくるのではないか」
「そこまで大仰な描き方はしないにしても、玩具が生命を宿すということがのちのち意味を持つのではないか」
と私の中で期待や予感が生じた。
それとは反対に、ぬいぐるみたちが「生きて」動くことにこれといって大した意味はないのかもしれない、という思いも同時によぎったが、なんらかの意味があるのではないかという期待や予感のほうが上回った。それほどまでに、ドラえもんがさらりと言ってのけた「ほんとに生きてるんだよ」の一言が私の心に刺さったのだ。
ちなみに、そうした期待や予感めいたものが生じたのは、映画『ねじ巻き都市冒険記』を初めて観たとき(あるいは原作マンガを初めて読んだとき)ではなかった。先に述べたように、初鑑賞時は物語にあまりのめり込めなかったし、作品内容に対する記憶が曖昧なのだ。だから、そんな期待や予感が生じたのは2回目の鑑賞時か、それ以降のことである。
すでに1度以上始まりから終わりまで観ている作品でありながら、その作品の序盤シーンを観て物語の先行きに予感を抱くというのもおかしな話ではあるが、『ねじ巻き都市冒険記』に関してはそういう心の働きが生じてしまった。
ともあれ、この作品は生命に関するなんらかの問題にアプローチしようとしているのでは……といった期待感や予感めいたものは、あるかたちで的中することになる。それも、「地球の生命誕生の理由が明らかになる」という、きわめて根本的で核心的な生命の問題がパッと描きだされるのだから、率直に言って仰天した。
のび太らの手でねじ巻き都市がつくられたその小惑星は、のび太らが訪れた時点ですでにとても緑豊かな星だった。物語が進むにつれて、小惑星をそんなふうに美しい星にしたのがどんな存在であるのかが明らかになっていく。のび太はその存在からコンタクトを受けて、言葉を交わす。
その存在は、「種まく者」と名乗った。
種まく者は、はるか昔、小惑星に生物の種(有機物質)をまいた。そこから生命体が芽生え、育ち、進化し、長大な時間の中で植物が栄える緑豊かな星になったのだ。
種まく者は、小惑星に生物の種をまくよりも昔に、地球や火星にも生物の種をまいたという。火星に芽生えた生命は他の天体の衝突によって台無しになってしまったものの、地球ではちゃんと生命が育ち、その進化の果てにわれわれ人間がいるというのである。
すなわち、種まく者は、地球の生命の造物主、ぶっちゃけて言えば神様のような存在なのだった。
種まく者当人は、のび太から「神様ってこと?」と問われて「ちょっと違うけど」と否定気味に答えているが、のび太と同じように私の頭にも「神様」という語がただちに浮かんだのだった。
地球に暮らす全生物のルーツとなる神様のごとき存在が名乗りでて、「どうして地球に生物が誕生したのか」という重大すぎる秘密を明かす……。そんな驚くべき、恐るべき、とてつもない事態が現出したのだから、これが仰天せずにいられようか。
藤子F先生の作品には、もうひとつの世界の造物主や異世界の神なども含めて神様的な存在がよく出てくる。だから、その意味では、ここで神様のような存在が出てきても藤子Fファン的には意外ではないのかもしれない。
ではあるものの、それでも私は、どこかの異世界やミニチュア的な世界ではなく、この地球に生きる全生命体の造物主たる存在がいよいよ『映画(大長編)ドラえもん』に登場した!ということにまず面食らったのだ。それも、あからさまな造物主である。アイデアのひねりとかちょっとしたギャグとかではなく、ダイレクトに造物主が登場するという……。その造物主が人並みに自己紹介したうえ、身の上話でもするように地球生命の秘密を明かしたことに、思わずのけぞりたくなった。
そのように種まく者の素性が明かされるシーンを観て、私は、種まく者のやったことが他人事ではなくこの自分にもかかわる重大事であるかのように感じてしまった。作中ののび太や数々のキャラクターたちにとって種まく者は紛れもなく造物主であるわけだが、それと同様に、自分の住むこの地球のこの生命たち、この人間たち、この私の造物主であるかのような感覚が不意に生じたのである。それはもちろん虚構と現実の混同なのだが、べつに本気で虚構と現実の区別がつかなくなったわけではない。理性的に区別できているのに、それでもなお、なぜか種まく者が自分たちの造物主であるかのような感じを受けたのだ。それはほんの一瞬だけの些細な感触のようなものだったが、そう感じてしまったことも私がこのシーンで妙に仰天した理由のひとつである。
種まく者は、私の心にさらなる爪痕を残した。あまりにも超絶的な存在である種まく者が堂々と登場して自分の素性を明かしたと思ったら、あとは任せたと物語からさっさと退場したのである。その引き際の鮮やかさというか唐突さというかあっさり具合というか……、私は仰天したまま呆気にとられるばかりだった。
あとは任せたと去っていったこの種まく者を、本作の執筆途中で他界した藤子F先生の姿と重ね合わせる人は少なくないようだ。
入場者プレゼント「ミニドラねじ巻きシティーカー」
種まく者は、先述のとおり、ねじ巻き都市がつくられた小惑星にも生命の種をまいていた。この小惑星を植物の楽園にしようと考えていたようだ。
小惑星の植物たちは、心を行動に表すことができる。深い地割れに落下したのび太の命を救ったのも植物たちだった。
意志を持つまでに進化した植物が人間の命を守ってくれる……。
その要素は、藤子F先生のSF短編『みどりの守り神』で描かれた植物のありようと相通ずるものがある。
特別割引券
『ねじ巻き都市冒険記』の作中では、生命のねじによって馬や豚などのぬいぐるみが生きて動くようになる。ドラえもんは、“タマゴコピーミラー”を使って生きたぬいぐるみの数をどんどん増やしていった。タマゴコピーミラーは、ごく簡単に言うと、生き物のコピーを手っ取り早くたくさんつくりだせるひみつ道具だ。
そうやってつくりだされた生きたぬいぐるみ動物たちは、じっさいの動物と同じような性質・生態を有していて、当初はのび太らにとって愛玩動物のような存在だった。
ところが、そのうち知能の高いぬいぐるみ動物が誕生する。豚のぬいぐるみ・ピーブがその第一号だった。ピーブは、生まれたばかりなのに言葉を話せて、読書が好きだった。のちにねじ巻き都市の市長となる彼は、落雷のエネルギーによって高い知能を得たようだ。
ぬいぐるみが高い知能を得た原因が本当に雷であるかを確かめようと、ドラえもんが人工的に雷を起こして実験するシーンがある。なにげなく私が好きなシーンだ。仮説を実験で立証しようとする科学的なスタンスを、ひとつのエピソードとしてさらりと挿し込んでいるのがいい。その実験で生まれたのが、豚のぬいぐるみ・プピーだった。
ピーブやプピーらに感化されたのか、ほかのぬいぐるみ動物たちも確実に進化していった。
もともとは、のび太らが遊び感覚でこしらえたねじ巻き都市。そこに知的な住民が暮らすようになり、社会が形成され、のび太らの手を離れて自治が行なわれていく。そんな過程が見られるところに、私好みの藤子Fテイスト、すこしふしぎな箱庭的世界の面白さが感じられて心を誘われた。
そうして、さらなる落雷によって、牛のアインモタイン、羊のトーマス・メーエジソンという天才が誕生するに至ったとき、私の中では大きな見せ場に触れたような高揚感がわきおこった。(原作マンガでは、トーマス・メーエジソンではなく、馬のレオナルド・ダ・ヒンチが登場している。こちらが映画版にも登場していたら、私の高揚感はもっと大きなものになっていただろう)
生命を持たないただのぬいぐるみだったものたちが、生命のねじによって命を吹き込まれ、生きて動く動物となった。非生命体から生命体へのとほうもない跳躍、とてつもない進化である。
生命を宿したぬいぐるみ動物たちは当初、家畜のようなありようをしていたが、そのうち言葉を話せる知的動物が突然変異的に生まれ、さらに偉人級の天才まで誕生した。本来なら長大な年月をかけてなされるはずの進化のプロセスが、極めて短期間のうちに達成されたのである。
ねじ巻き都市は、著しい生命進化が非常にインスタントなかたちで達成された空間なのだった。
劇場限定グッズ各種
『のび太とアニマル惑星』『のび太と雲の王国』で描かれたエコロジー思想、エコ社会化した異世界の風景が、それら2作品ほどの強度ではないものの、『ねじ巻き都市冒険記』でも見て取れる。ねじ巻き都市のエコ化を推進する力となったのが、アインモタインとトーマス・メーエジソン、2頭の天才だった。
ねじ巻き都市で建設会社を運営するジャイアンと自動車や船を走らせるスネ夫が法廷に立たされ、2頭の天才によって環境破壊行為を追及される。その法廷シーンで2頭の天才は、エネルギーをソーラーバッテリーへ切り替えるよう要請したり、ねじ巻き都市ではビルの材料として扱いやすく丈夫で軽い無公害物質のセラミックを使用していることを説明したりする。
ねじ巻き都市の創建者の一員であるにもかかわらず、住民たちから悪者扱いを受けてしまったジャイアンとスネ夫が少し気の毒だったが、ともあれ、その徹底した理想的エコ社会のありように『アニマル惑星』や『雲の王国』で観た風景と響き合うものを感じた。
スタンプ帳
『ねじ巻き都市冒険記』において、のび太たちやねじ巻き都市の住民らの敵となる悪者が、熊虎鬼五郎である。36歳、前科100犯の凶悪な脱獄囚だ。鬼五郎は、ひょんなことから小惑星にやってきて、ねじ巻き都市の乗っとりをくわだてる。
もちろん、そんな鬼五郎との戦いはこの映画の大きな見どころであるが、本作における鬼五郎の存在感は、鬼五郎の人数が複数化することで思いきり発揮される。先ほど紹介したタマゴコピーミラーによって鬼五郎のコピーが12人も生まれ、オリジナルの1人と合わせて13人の鬼五郎が同じ場所に存在することになるのだ。
まったく同じ人物が常に13人で行動を共にするというその異様な光景に、まず単純なインパクトがある。悪事を働くときも、戦うときも、移動するときも、何をするにも同一の13人がゾロゾロと出てくるのだから。
そのうえで私がとりわけ注目したいのが、13人の同一人物がいてもその集団を統率するのは結局のところオリジナルの鬼五郎であったことだ。コピーが何人いても、オリジナルがいちばん偉く、誰もオリジナルにはさからわない。オリジナルがリーダーシップをとることで、13人の鬼五郎軍団は秩序を保つのである。
そんな、同一人物ばかりの超均質的な集団の中でオリジナルが圧倒的に優位な立場にあるという状況が、オリジナルとコピーの関係性という観点から、じつに興味深く感じられる。ろくな議論もなく、選挙もクジも闘争もないままに、1人のオリジナルが総勢13人で構成された同一人物グループの中心をなして場を仕切ってしまう。多数のコピーよりも1人のオリジナルが断然強者なのだ。
それに加え、さらに私が興味をかき立てられたのが、まったく同じ姿をした鬼五郎軍団の中に1人だけ、ほんの少し外見の異なる者がいたことだ。
1人だけ、顔にホクロのある鬼五郎がいたのだ。
鼻の下のあたりにひとつホクロがあるだけだから、外見の相違といってもほんのささやかな違いである。ほんのささやかな違いなのに、それが本人にたびたび不利益を招くことになる。
ホクロがひとつあるというそれだけのことで、リーダーであるオリジナル鬼五郎に目をつけられ、いちばん重い荷物を運ばされたり、危険かもしれない場所へ誰よりも先に行かされたり。リーダーから最もこきつかわれる標的になってしまったのだ。
それは有徴性とでも言うのだろうか。極度の同質的集団の中では、たったひとつの小さなホクロという徴があるだけで変に目立ち、なにかと不利益をこうむってしまう。それ自体は有害でもなんでもなく、ただぽつんとついているだけのホクロが、全員が同じ顔をした集団の中ではネガティブなシンボルとして機能してしまうのだ。
ホクロのついた鬼五郎だけが、凶暴な鬼五郎軍団にあって唯一心やさしい性格だったことは、どこか意味深である。
ホクロ鬼五郎は、悪の軍団の中でただ1人だけ善の心の持ち主だった。13人の鬼五郎の中では極めて異端の1人だったのだ。
のび太やその仲間たちとの戦いに敗れた13人の鬼五郎軍団は、13人のままにしておけないからと1人の鬼五郎に戻される。そういう処置がとられるのだが、なんの加減か、1人に戻った鬼五郎はホクロの鬼五郎だった。
13人に増えた鬼五郎が1人の状態に戻るのであれば、12人のコピーが1人のオリジナルに吸収されてオリジナル鬼五郎だけが残る、というのが道理だろう。
だが、そうはならなかった。コピーであり異端であったはずのホクロ鬼五郎が、唯一の鬼五郎として残ったのである。
ホクロがついていることでいつも損をしていたホクロ鬼五郎は、最後の最後にそうやって報われた。大勢の中で異質な1人だったホクロ鬼五郎は、最後に1人残った時点で新たなオリジナル鬼五郎になったとも言える。
ホクロ鬼五郎は善良な性格だったから、凶悪な犯罪者的人格の鬼五郎はすべていなくなったことになる。
のび太たちが鬼五郎軍団との戦いに勝ったことで、この物語における悪は制圧されたわけだが、その後13人の鬼五郎軍団が心やさしいホクロ鬼五郎1人に収斂されたことによって、その悪は制圧されただけでなく完全に消え失せたことになる。悪は二重に敗北したのである。
鼻の下のあたりにある、たったひとつのホクロ。それがこんなにも意味を持つ徴として描かれたことに私は感服した。個人的には、そのことがこの映画の特筆すべき見どころとなった。
《第6回へ続く》
『モッコロくん』を読んで藤子マンガに惹かれ、小学校の卒業文集には「ドラえもんは永遠に不滅だ!」と書きました。
中学で熱狂的な藤子ファンになり、今でもまだ熱烈な藤子ファンです。

記事一覧はこちら