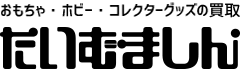松田聖子・セピア色のフォトグラフ~36年の後に~
キーボードとアコースティックギターのユニゾンが作る、明るい透明感にみちた旋律がステップを踏んで、一音づつ音程の四つの階段を駆け上がりきる。と同時に、ドラムの軽やかな一撃が入り、次にはベースとブラスのたった一音だけのユニゾンが間髪を入れずに作る一瞬のブレイク。
短いが考え抜かれたそのイントロに跳ね上げられ、わずかに擦れたとろけるような松田聖子のあの声が、ふと見上げた秋の高い空から舞い落ちるかのように、いきなりの再高音からのサビのメロディーを奏で始める。
“光と陰の中で、腕をくんでいるぅ~♪”
メロディーを紡ぐ聖子の甘い声は、一旦、低音部に沈むが、このフレーズの最終部分でいま一度、高音部に跳ね上がる。この時、聖子の声は、消え入りそうな不安定さをわずかに垣間見せるが、それは溢れ出る過ぎ去りゆくものへの心の揺らぎだ。
そして特徴的な舌足らずな”る”の発音が、そして時に低音部でわずかに震えるキャンディヴォイスが、聴くものの胸を掻きむしる。やがてブラスが合いの手を入れ、聖子の歌声と溶け合いながら、紡ぎ出してゆくのは、あの頃、誰にでもありそうで実際にはありえなかった、それなのに、永遠に失われたと感じてしまう、風街の蜃気楼のような風景だ。
一番好きな松田聖子の歌をあげろ、と言われると、一千一秒物語か蒼いフォトグラフのどちらかだといつも言っている。好きな聖子の曲は多すぎるし、実際にはその場の気分次第で選ぶ曲は日替わりだ。その時、その場で聴いている曲こそがベストと言っても良い。それでもこの二曲を常に上げるのは、一番ではないにしろ、好きな曲を5曲選べと言われれれば、この二曲はいつだって必ず入ってくるからだ。
蒼いフォトグラフが発売された27年前の1983年10月28日、僕は大学5年生だった(笑)。誰だって若い頃は馬鹿なことのひとつやふたつをしでかしてしまうものだ。だが、僕の場合は、その度が過ぎていて、何年か経ては冗談の種にできるという範囲ではなかった(注1)。その上、本人はそうした愚行を至って真剣、脇目もふらずに取り組んでいたのだから手に負えない。その結果、大学を4年で終わらせなかった、いや、終わらせ損なった・・・のかな?もはや、詳しい事情は本当に覚えていない。それでも、この頃にはさすがにいつまでもこんなことはしていられない、と少々は正気に戻り、何をするか、何処に行くのか、社会に出るのか?まずは覚悟を決めよう、混乱した頭を抱えてやたらに焦っていた。
そんな時に出逢ったこの曲、移ろいゆく青春の只中、それが終わろうとしていることを自覚した歌のヒロインの、口には出さない過去への決別と、新たな旅たちへの決意を、聖子はあの甘い声に、哀切をちょっぴり混ぜながらも、軽やかに描き出していた。
その声は僕にとって、まるで聖子からの個人的で親密感に溢れたメッセージのように響いた。まるで“あなただけじゃないのよ”と耳元で囁いてくれるような。
‟一度、破いて、テープで貼った蒼いフォトグラフ“
この頃、確かに聖子も岐路に立とうとしていた。アイドルとして芸能界の頂点に立とうとしていたがゆえに、そんなものは早やかに過ぎ去ってしまうのでは、という恐れにおののきながらも、芸能人としてよりスケールアップしたキャリアを作りたいという野望と、憧れの人との結婚でいったんキャリアに休止符を打ちたいという相反する選択に人知れず思い悩んでいただろう。
そして、そのどちらを取るにせよ、今までの自分が大きく変わらざるを得ず、そのための新たなステップに進もうとしていたのが1983年の松田聖子だった。
もっとも、そんな個人の事情とは別に、この年の聖子は表向き絶好調で、その怒涛の勢いは、デビューした80年にも劣らないほど。リリースするシングルもアルバムも音楽的には充実しきっていたし、映画やテレビ出演などの芸能活動もこれ以上はないといえるほど活発だった。
ただ、そんな表向きの彼女の勢いと、人知れず隠した内心をはっきりと表していたのは髪型で、この年から翌年にかけて、彼女は頻繁に髪型を変えだす(注2)。
テレビで見る聖子は出演する番組毎に違った髪型で登場し、そのどれもが新鮮でとびきり可愛かったにもかかわらず、次の番組ではあっさりとその髪型を捨て去り、別な髪型に変えていった。
それはどのような事に挑んでも決して悪い結果など起きようがないという自信と、前向きのチャレンジ精神の表れでもあったろうけど、その陰には何が何でも、あらゆる手を駆使して芸能界アイドル戦線のトップを守り切らなくては、という追い立てられるような不安とが、同時に透けて見えていた。
今になって振り返ると、聖子も僕も人生の岐路に立っていたとはいえ、なぜこの曲の聖子の声に自分を重ねることができたのか、苦笑を禁じ得ない。
僕の83年は、この歌の明るく爽やかなものとは程遠く、まして聖子の輝かしい日々とはまるで別の、暗室の油虫のようなゴソゴソ、ぐちゃぐちゃとした救いの見えない日々の繰り返しが、何の結果を出せるわけでもなく、無駄に過ぎ去ろうとしていた。聖子は”一度、破いて、テープで貼った蒼いフォトグラフ”と歌っていたけど、この頃の僕には自分を写した写真自体がほとんど無いのだ。とてもじゃないが、自分の姿を見たくも、残したくもなかったからだ。
といって、僕が聖子とのあまりの違いを嘆き、その眩さに気後れをしていたか、と言えばそんなことはない。所詮、聖子は別な世界の住人。彼女は彼女の世界で輝き、薄汚れた僕の世界の数少ない灯になってくれればそれでよい。だからレコードは買い続けていたし、彼女のコンサートに最も頻繁に行ったのもこの年だったはずだ。
きっと、あれは聖子のムーンライトマジック、どんな惨めな思いを抱えるファンにも聖子と同じ夢を見させてしまう魔力のせいだったに違いない。
“今、一瞬、あなたが好きよ、明日になればわからないわ”
頭サビが終わり、曲の盛り上がりが一段落すると、キーボードとリズムギターが奏でるゆったりとしたさざ波のようなリフが、音数こそ多くないけれど、そよ風に転がるようなエレピのオブリガードに寄り添われて繰り返される。その音の波の上を、聖子は決して声を張り上げたりすることなく、呟くように松本隆が書いた繊細な歌詞を歌い綴ってゆく。
歌の中で聖子が化身するのは、今でいうツンデレだ。うつむき加減で、小声でぽつりと気を持たせるようなことを言ったかと思うと、次にはプンと向こうをむいて素知らぬ顔でとっとと前を行ってしまう。
不意をつかれて、何を聴いたのかさえ確信を持てず、僕はあわてて君に追いつつくけど、君は振り向きさえしない。そして、昼下がりの柔らかな陽光に酔いしれるように目を閉じながら、口元には微かに微笑みを浮かべ、何か声にならない言葉を囁く。港から吹いてくる海風が耳元の髪を軽くたなびかせ、君の言葉も運び去ってしまう・・・
“みんな重い見えない荷物、肩の上に抱えてたわ‟
初めてこの曲を聴き、この一節を聴いたとき、少し驚いたのを覚えている。
ここでの‟みんな“は、歌の中の“わたし”も‟あなた“も、そして聖子自身や歌の聞き手まで、すべてを含んだ‟私たち”という意味だろう。そして聖子の曲の中で、こうした同世代に対してのねぎらいとも聞こえるメッセージと思えるものに出逢ったのは初めてだったからだ。
実際、知りうる限りで、聖子の80年代の曲の中で、“みんな”とか”私たち‟という言葉が歌詞に出てくるものは、初期の三浦徳子の作品、これ以後の作品を入れても、他にはないはずだ、ただ一曲を除いて。それは聖子にとって、明確な唯一のメッセージソングである瑠璃色の地球だ(注3)。つまり、この曲も、非常に遠回しであるけれど、それだけに巧妙な松本隆流のメッセージソングなのだ。
松本隆は、商品としての大衆歌謡の華やかな外面の裏側に、彼自身の個人的な心象風景をそっとしのび込ませ、それを風街と呼んでいる。
彼の作品のベスト&集大成であるはずの風街図鑑によれば、蒼いフォトグラフの詞は、彼が大学一年生の時の横浜でのデートの経験を基にこの曲の詞を書いたという。大学は学生運動が盛んな不安と渾沌の時代で、彼自身も音楽家のプロになろうかどうかと悩んでいた時期だったそうだが、同時に“それは一番美しい時期だった”とも書いている。
松本隆全盛期の作品の中で、ここまで赤裸々に、個人的でさえある風街を詠み込んだ歌詞は、“はっぴいえんど”関連の作品群を除けば、稀ではないだろうか(注4)。そして、それが出来たのは、83年の聖子の充実ぶりへの信頼と、聖子の歌声の特徴をすっかり把握した上で明るいながらにも哀感を漂わせた、詞と一体になった繊細なメロディーを作ったユーミン=呉田軽穂がいたからこそだろう。
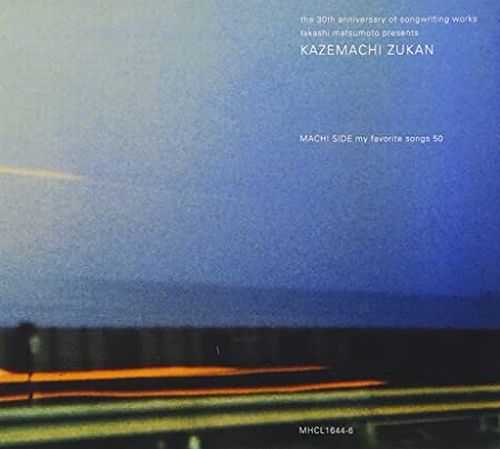
僕の進路がなんとか決着ができたのは83年の暮れ、ちょうど、蒼いフォトグラフがテレビで流れ始めた頃だったと思う。その頃は職安といったハローワークで、ふとしたはずみに従業員数が10人にも満たない小さな、しかもベトナム貿易専門という奇妙な会社を見つけたのだ。募集するのは海外出張要員とある。当時のベトナムは、今とは全く違い、定期便もなく人の往来もない、日本に最も縁遠い、戦争ばかりをしている”忘れ去られた貧しい社会主義国“でしかなかった(注5)。
だが、そんなことはどうでも良かった。一刻も早く、こんな日本、いや自分自身から、どこか誰も知らない、誰からも知られていないところへ逃げ出したかったからだ。従業員数も数人なら、そう何年も待たなくてもさっさと海外出張や駐在のチャンスがもらえるだろう。聖子はカセットにでもダビング録音して持って行けばよいのだ。
‟いちばん、綺麗な風にあなたと吹かれていたから‟
翌年の春、なんとか必要最低限のラインで単位を揃えて大学を卒業すると、僕は首尾よく、その小さな貿易会社に勤めだした。
その直後の4月に行われたのが、テレビでも放映された聖子にとって三度目になる武道館コンサート、セイコ・ファンタスティックフライだ。コンサートは4月22日と23日の二度、武道館で行われているが、今となってはどちらの日のライブに参加したのかもうわからない。
第一部のヒット曲メドレーが夏の扉で終わって(注6)、聖子は一旦、退場。その後、あの印象的な四段飛びのイントロが鳴り響いた瞬間、僕は小躍りした。蒼いフォトグラフであることがすぐ分かったからだ。そして、聖子がこの曲を生歌で披露するのは、この時が初めての筈だ。
ただし、この時のヴァージョンではすぐに歌が始まるのでなく、姿の見えない聖子の声だけによるバンドメンバーの紹介があり、そのため通常より長い前奏が付け加えられていた。そして、もう一度、高らかにあのイントロが鳴り響くと、おもむろに曲に合わせたかのような青いロングドレスと同色のターバンで髪を巻いた聖子がスポットライトに中に浮かび上がった(注7)。
そして輝くような、同時に切なく酸っぱい、光の中で一抹の陰がさすような声が聖子の華奢な体から溢れだした。その声は即座に会場全体を優しく包み込み、そして、聖子は光る円形ステージの上をゆったりとした波に漂うように揺れ続けた(注8)。
その姿は、83年以降、大人聖子、アイドルでないアーチスト聖子を強調し出したステージ演出の中では、最もキュートで魅力的な姿のひとつだったろう。
ファンタスティックフライは、期せずして僕にとっては若き聖子、そして自分自身へのサヨナラを告げるコンサートとなった。このコンサートの数か月後、The 9th waveを買った直後に僕は日本を離れ、以降、1996年までを主に仕事先のベトナムで過ごすことなったからだ。
カセットに落として持って行ったThe 9th Waveだったが、結局、聴いたのはほんの数回程度。希望した通り、誰も知らなければ知られてもいない新たな土地で生活し、そこに馴染むうちに、聖子はあっという間に過去のものとなった。
そして以後、四半世紀の間、僕は聖子を忘却の彼方に追いやった。結婚のニュースは聞こえてきたが、Supremeも瑠璃色の地球も当時は全く聴くことも知ることもないままに過ぎた。
帰国時は丁度、”あなたに逢いたくて”がヒットしていた時機のはずだが、そんな曲でさえもファン復帰まで僕の耳に入ることもなかった。
〝今の青さを忘れないでね、蒼いフォトグラフ“
ファンに復帰して十年、折りに触れて訊き返すことの多い蒼いフォトグラフ。だが、僕個人に蒼いフォトグラフはない。あの頃、一番綺麗な風に吹かれることはできなかったし、輝いた時でもなかった。だから、仮にそんな写真があったとしても、それは、もともとどす黒く汚れてしまった写真でしかないのであり、そんなものは何時までもセピア色などにはならないだろう。
それでも、この曲は37年前も、そして今も、相変わらず僕の心をしめつけ続ける。それは、聖子によって歌われる蒼いフォトグラフとは、単に青春時代の甘酸っぱい、恋の思い出というだけに留まらない、生きる上でより決定的なことに思えるからだ。
それは経験したことによって、その後の人生の中で繰り返しその経験を生きることをやめなられなくなるような、胸中に永遠に留まる過去の一瞬間、追憶によって凝結される神話的な経験、それそのものは過ぎ去り、形を失くしてゆくことで、その形を未来に担保してしまうもの。
そんな経験は往々に若い頃に起き、以後、生きるということは、あの失われた時が、永遠に続く今の自分を作り続けることになるだろう。だから、あの時の青さも決してなくなることはない。
おそらく、そんな蒼いフォトグラフは人によってその色や形は違え、誰にでもあるものなのだ。
不思議なことだが、傍から見れば人が羨むような素晴らしい80年代を過ごしたに違いない聖子自身は、この時代、いや彼女の過去そのものを振り返ることはほとんど無かったように思える。もちろん、コンサートでは、この時代のヒット曲は欠かさず歌い続けて来たし、TV番組やインタビューで問われれば、この時代のエピソードを語っている。
だが、そうして歌われる聖子のヒット曲は、大衆歌手にとって当たり前のものであるファンに対するサービスであって、彼女の個人的な思い入れは深く感じられなかったし、彼女の語る内容は表面的なエピソードという印象が拭い難かった。そして、実際に彼女自身が歌った曲には、松本隆が作ったものを除けば、過去を引きずるような内容のものはほとんどない(注9)。きっと、彼女には未来を見据えて、今、しなくてはならないことが常にあまりにたくさんあり、過去を反芻する時間などなかったのだろう。それに、芸能人、歌手としてあまりに大きな存在となった彼女の青春は、彼女個人として消化するにはあまりに大きく、それを咀嚼するには難しすぎたのかもしれない。
しかし、聖子の最新アルバムSeiko Matsuda 2020と10月のOn Line Liveを聴いたとき、恐らく多くのファンが気付いたはずだ。2020年の聖子が歌う80年代のヒット曲はもはや単なる過去曲のヒットパレードのサービスでないし、今の音域と新しい編曲で歌ったという技術的なリメイクで済ませられるものでもないということを。
歌はかつての自分をなぞることをやめ、今の聖子の心情を反映したものに解釈し直されていたが、そこには確かにあの時の聖子の反響がこだましていた。それは聖子が歌を通じて、かつての彼女自身、そしてかつての彼女に向けられたファンの想いを抱きとめているかのようだった。
過去は形無くなるなるが、永遠の中に生きる。オンライン・ライブでの赤いスイートピーを歌っている時、“なぜ、あなたが時計を見る度”の部分で腕時計を見るポーズをとった聖子。その目に映る想像の時計は‟永遠‟という以外のどの時間を指すことができたろうか。
聖子の蒼いフォトグラフは、一度、破られ、セピア色になることによって、いつのまにか、松本隆が30年を経て聖子に贈った〝永遠のもっと果て”に転生していたのである。
(了)
注1: 本文では敢えてぼかしたが、僕が夢中になっていたのは、当時でさえ時代遅れで、大多数のひとから白眼視された‟極左政治運動‟である。その時の自分の行動とその方法、考えの拙さ、がさつさは生涯の悔いとなっている。
一方で、それを通じて目指した方向性は大きな部分で間違っていないと、未だに信じている。ただし、政治において手段の間違いは目的を正当化できないし、政治が容赦なく人を傷つける恐ろしさは骨身に感じているので、他人に対し、政治的な影響を及ぼそうとすることには、出来る限り抑制的であるべきと自分に課している。
注2: 聖子が結婚後に夜のヒットスタジオに復帰を果たした時、80年から85年までの全出演回をダイジェストにして放映したが、それがYou Tubeに上がっているので、髪型の変遷を確認して欲しい。それにしても髪型をこれほど変えた芸能人は空前絶後ではないだろうか。
注3: 瑠璃色の地球では、‟私たち‟の他に、‟誰もが‟、‟人“という三つの言葉をほぼ同じニュアンスで、私とあなたを含むすべての人という意味で使用している。意味は同じでも、違う言葉を使い分けるのが、言葉の職人である詩人、松本隆らしいところだ。
注4: 80年代の大瀧詠一とのA Long VacationとEach Timeの中の作品には、一聴して小説で言えば、私小説に似た感触の作品がいくつかある‐例えば君は天然色や雨のウエンズデイ⁻が、これはやはり盟友との作品だからだろう。そして、松本隆がペースを落とし、ほぼ半隠居生活(?)となった2000年以降の作品になると、ほとんどの作品に松本隆の個人的心象風景が全盛期の作品以上に色濃く表れるようになる。これは年を重ねた彼自身が、もはや商業作品としての枠組みをあまり考えなくなったためだろう。聖子との1999年の永遠の少女にも、大村雅朗さんへの追悼である‟櫻の園‟の他にも、‟エメラルド海岸‟、‟カモメの舞う岬‟‟心のキャッチボール“などは、聖子のキャラクター設定を超えて、松本隆の個人的な思い入れがより強く感じられる。実は、この思い入れは当時の聖子には少々、重たすぎるように感じられたのではないか?そんな風に思っている。
注5: 1980年代当時、ベトナムで働く数少ない日本人同士の間では、‟パリより遠いベトナム‟と自嘲しあっていた。その頃、ベトナムに行くためには一度、タイのバンコクに飛んで一泊、翌日(それも週3日ほどの限られた曜日)にやっと到着。総計で25時間以上かかっていた。
注6 : セイコ・ファンタスティック・フライは4月24日の回が、当時、フジテレビでテレビ放映され、かつてはYou Tube等にも全編が上がっていたが、今は残念ながら、部分的なものでしか残っていない。蒼いフォトグラフはTV放映からはカットされてしまっているが、これはこの曲がテーマ曲になったテレビドラマ“青が散る”がTBSのものだったためだろう。実際のパフォーマンスはテレビ放映されたSquall-夏の扉のメドレーの後、次のSweet Memoriesの前に行われた。ファンタスティック・フライでは最初こそ、髪の毛爆発スタイルの聖子に驚かされたが、その後の青ドレス、可愛い背中を大胆に出した黒いパーティ・ドレス風のものなど伊集院静演出以降のものでは珍しく(?)センスの良いものが多かったと思う。
注7: この時の衣装はYou Tubeでまだ生きている動画、このコンサートでの“瞳はダイアモンド”で見ることができる。ただ、歌の出来が最高だったのは、この衣装での最後の曲となったピーチシャーベット。You Tubeで松田聖子 ピーチシャーベットで検索すれば多少、画像は細工されているが、その歌を聴くことができるが絶品だ。
注8: 同じ年の12月15日に聖子はGolden Jukeというコンサートを行い、そこではアンコールでの一曲目で蒼いフォトグラフを歌っている。このコンサートもTV放映され、You Tubeで全篇、視聴可能なので未見の方は是非とも。ファンタスティックフライと同じように客席が円形ステージを囲む演出で、時期的に近いこともあり、歌も非常に近いものだったと思われる。蒼いフォトグラフはアンコールということもあり、聖子自身も気分が高まっていて、所々、やや声が上ずり気味だが、いいパフォーマンスだ。私事だが、このコンサートの日、私は既にハノイにいた。もう年末に近い冬のハノイは熱帯にもかかわらず案外に寒くなり、小糠雨が一日中降る陰鬱な日々が続くことが多い。経済はどん底で人々は貧しく、活気もなく、街全体が雨に朽ち果てていくようで、さすがにこの頃は多少のホームシックを感じた。丁度、その時、聖子は武道館で熱狂する大観衆の前でこの曲を歌っていたというわけだ。
注9: 20th、30th、40th Partyなどの周年記念曲を、聖子なりの過去の反芻といえるだろうか?僕はこれらの曲は聖子のファン向けのサービスジョークだろうと思う。
1960年生まれ。
様々な音との出会いを求めて世界を彷徨い続けていますが、ふとした拍子に立ち戻るのは、ジョアン・ジルベルトと松田聖子、そしてエリック・ドルフィーの音の世界。聖ジュネで示された方法論を応用して聖子を理解し、語り尽くすのが夢。
プロフィール写真はJose Antonio Mendezの「ESCRIBE SOLO PARA ENAMORADOS/フィーリンの真実」レコードジャケットより。
Twitter ID:@bossacoubana

記事一覧はこちら