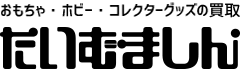松田聖子-In her life- 第一部(前編)<A perfect girl for Kawaii 可愛いにうってつけの少女>
松田聖子 -In her life-
But of all these friends and lovers
There is no one compares with you
<第一部>
-前編-
後から考えてみれば、その言葉ひとつで、自分の一生が決定されたとしか思えないキーワードが人それぞれに幾つか存在する。その言葉を人が自分自身の中から自発的に見出だすということはほぼない。それは多くの場合、他人から何気にかけられた平凡な言葉だが、人を固定し、塗り固めてしまうのだ。人は変身を余儀なくされ、そのため以前とは別な世界に生きることになってしまう。
松田聖子にとって、そうした決定的な言葉はふたつあり、ひとつは松田聖子として形作られる以前の幼年時代から子供時代の蒲池法子に決定的に影響を及ぼし、彼女を将来の松田聖子というアイドル歌手になるべく形作っていくことになる。だが単なるアイドル歌手というだけで松田聖子は終わらなかった。年齢的にいささかとうの立った遅いデビューを1980年になってやっと果たしたこの女性歌手は、ただヒット曲を連発しただけでなく、その歌声は80年代に成熟のピークを迎えていた日本の大衆音楽の最良の部分を体現し、それを誰よりも広く大衆化させるのに貢献した。同時に、私生活での恋愛、結婚、出産、そして復帰、度重なるスキャンダル等を乗り越え、日本社会のある一世代まるごとの女性に影響を与えるアイコンとしての芸能人となり、そして現在に至っている。そこには蒲池法子から歌手松田聖子となった時とは、また違った別な松田聖子への変貌があったはずであり、それを決定的にした別の言葉があったはずだ。
そうした二つの決定的な言葉とは、ひとつが‟可愛い‟であり、もうひとつは“ぶりっ子”だと私は思っている。
可愛いにうってつけの少女
~A perfect girl for Kawaii ! (注1)
“可愛いね、君”
離れてるから、“ねえ、ひとりきりなの?”
あなたはあわてて飛んできて、私の手をつかむのよ
“可愛い‟という言葉は、現代日本社会でもっとも繁雑に使われ、その影響力も飛び抜けて強いもののひとつだ。特にこの国の若い女性たちにとっては、“可愛い”は生きる上での最も重要な価値基準と言っていいかもしれない。そして、今や‟可愛い‟は日本を超えて世界的にも、現代日本のポップカルチャーを代表する言葉として国際的にも広く認知されるようになっているという。
では、この言葉を最も似つかわしい、あるいは体現する人間といえば…私は松田聖子と言ってしまいたいのだが、残念ながら、“それは違うでしょう、昔はともかく!”と、おっしゃる方も、今、この時代にあっては多数いるであろうことは容易に想像がつく。というのは“可愛い”という言葉は後述するように、絶対的な年齢の若さと強い関連があり、既に50代も半ばを過ぎ、というより率直に還暦間近(失礼!)の聖子には、それだけで不利に働く言葉だからだ。とはいえ、聖子がいったんステージに立てば、今でも会場中から“かわぃーい”という歓声が飛ぶし、You Tubeやニコ動の80年代の聖子動画には必ず‟何という可愛さ!“というような賛嘆のコメントが並ぶ。そして聖子は40年になろうとする芸能生活を、常にこの言葉とともに歩んできたわけで、‟可愛い‟と言われた回数の総量でいえば、依然として聖子が日本でトップのひとり、それどころか、若い時のある短期間に爆発的にそのように言われるだけでなく、その後も今に至るまで、コンスタントに呼ばれ続けているという点でダントツのトップと言ってよいのではないだろうか。
芸能人としては吉永小百合が似たような例としては挙げられだろうし、しかも活動期間は聖子より長いのだが、彼女は可愛いと同時に美しいと呼ばれているケースが相当多い。‟可愛い”のレジェンドやはり聖子なのだ・・・と私は思う。
この可愛いという言葉、一般的には‟愛嬌のある外観をもつ様子‟という程度の意味でとられているが、現在では、その言葉のあまりに頻繁で広範な適用がその本来の意味を拡散させ、内実がわかり難くなってしまっている。
一例を挙げよう。これを自慢と言ってよいのかどうかわからないのだが、先日、私は会社で若い女性社員に“可愛い”と言われてしまったのである。その時、私は目先の仕事に気を取られ過ぎ、彼女の質問に対し、いささか的外れの返答をしてしまったらしいのだが、その返答のトンチンカンさ具合と、それに気づいた後の私の狼狽えた反応ぶりに、彼女は愛嬌を感じたらしく、可愛い!と笑いながら叫んでくれたわけだ。が、この時の“可愛い”をYou Tubeで80年代前半の聖子のテレビパフォーマンスを見た時に、私たちが感じる”可愛い‟では、同じ言葉が使われているとはいえ、その意味も使用のニュアンスもかなり違うものになっていることは明白だ。そもそも80年代前半の聖子と現在の私のほぼ白髪でしょぼくれてしまった初老のおっさんの風貌に、一体、何の共通点が見つけられるだろうか。やはりこのふたつの“可愛い”には大きな違いがあると言わざるを得ない。
このように、今では、あまりに多様化してしまった“可愛い”ではあるが、しかし、そのもともとの意味は幼児を対象にしたものだと私は思っている。幼児、というより端的に赤ちゃんと言ってしまって良いと思うが、その柔らかみを感じさせ、それゆえに他者に対し攻撃的、威圧的な印象を持たせない、丸みを帯びた曲線的な体の輪郭、大きな目とふっくらとした頬、見たものの保護感情をくすぐる小さな体躯と、発達の未熟さからくる不器用でたどたどしい身振りは可愛さの要素として不可欠なものだ。ただしそこには、それだけに留まらない生命力の発露を十分に感じさせる感情の躍動感も同時に必須となる。だから、動きもままならない生後間もない時期より、赤ちゃん自身の躍動をより肯定的な感情を表現できる‟笑い”が豊かな時期の方が望ましい。
こうした赤ちゃんの様子を見た時、それによって生じる私たち内部に湧き出る赤ちゃんに対する肯定的な感情の動きこそが、可愛いの実体であり、それを喚起させるものを、僕らは‟可愛い‟と呼んで肯定的な価値を与えるのである。また、赤ちゃんはその未成熟さゆえに、その感情表現は複雑さを伴わず、一途でストレートであり、それこそが、私たちが感じる純粋さ=イノセンスとされ、これもまたやはり可愛さの重要な一要素となる。
そして、これに似た構造で感情の動きを誘発するものが、幼児以外の他の対象にも見つけられる場合、これも我々は、通常、可愛いと呼んで肯定的に捉える(注2)。既に幼年期を過ぎた少年や少女たちが可愛い、と呼ばれるのは、多少、身体的は大きくなり、曲線的な外観も失われてしまっても、外見は幼児的な特徴を色濃く残しているのに加え、依然として周囲からの保護は必要な無力な存在と見なされる一方で、生命力の躍動感は幼児期よりも溌剌として感じられるからだ。しかし、子供たちは成長し、その身体的特徴は赤ちゃん期の特徴を加速度的に失ってゆき、同時に自立度を増してゆく、つまり保護が不要になるにつれ、彼らは”可愛い”と呼ばれる機会を徐々に失ってゆく。
一方で、この言葉の適用頻度には男女に大きな差があり、しかも年齢と共にその差がついてゆく。男性が成人後に可愛いと呼ばれることは、むしろ男性的な逞しさや、強さに欠けるということで、現在でさえ、当の男性には気恥ずかしい感情を生む。ところが、女性の場合は、可愛いという言葉は、成人前はもちろん、成人後でさえ相当長い期間使用され、男性の場合とは比べられないほどの影響力を持つ。これは、男性よりも女性の体の方が、小柄で曲線的な外観を持つ場合が多いことのためもあるし、それ以上に、現代社会でも依然として女性は社会ではより低い位置で守られるべき存在であり、だが同時に生命力の発露という魅力を期待されるべきという前提での構造が強固に残っているためだろう。だから、女性がフェミニズム的視点から敢えて”可愛い”を拒否するということも、特に現代欧米社会では決して珍しい事ではない。
このように‟可愛い‟の基本的な意味とその特徴を見てみると、松田聖子の、特にデビューから80年代前半のアイドル全盛時の容姿は典型的な“可愛い”に相応しいことがわかる。その“ベイビー”フェイスの顔、つまり‟つぶら“な瞳、色白の肌とうっすらとピンク色に上気したふっくらとした頬、ただし美人と呼ばれるほどの超絶的な造作の整い方はなくややありきたり、だが、そこに無邪気そうな満面の笑顔が現れると、容姿総体としてはとても親しみやすさを感じさせるものとなる。そんな顔を支え、飾るのは、新鮮な女性らしさを思い切り強調した髪型=聖子カット、狭い肩幅と長い首に代表される華奢で頼り無げ、それゆえ思わず抱きしめて守ってあげたくなる体格だ(注3)。
そんな少女からは、意外にも力強く、ぴちぴちのバネの思わせる弾力性と生気に溢れている歌声が発せられる。ただし、その歌唱はパワフルではあっても、聞き手に威圧感を与えるような重量感と緊張感はなく、あくまで軽やかでスピーディ、明るく幸福感に満ちた歌を聞かせる、これらすべてが、“可愛い”の成立要件のひとつひとつを真正面からヒットさせている。
だが、聖子の‟可愛い‟がそれをいかに的確に捉えていようが、単なる容姿や雰囲気だけに留まるなら、あの80年代に社会の雰囲気まで変えた大ブームとその後への影響力、今に至るまでつづく根強い支持がなぜ起こりえたかが説明できない。聖子ほど的確かどうかは別にして、‟可愛い‟アイドルはいつだって存在していたし、今後も新たに生まれ続けるだろう。しかし、こうした‟可愛い‟アイドル達の中で聖子のような存在に到達できたものは今までにはいないし、今後もいないだろう。
そして聖子自身が年齢を重ねれば、典型的な“可愛い”からは徐々にであれ、離れざるを得ないのだ。であればこそ、聖子の“可愛い”には独自の何かがあるのだ。
誰もが知るように、後に松田聖子となる蒲池法子は1962年3月10日に福岡県久留米市で生まれた。そして、彼女こそ、その生まれ、生育環境、彼女自身の資質、全ての点においてまさに‟可愛い“にうってつけの少女だった。法子の父親は公務員(社会保険庁=厚生省直属の事務官)、母親は結婚前には看護婦だったが、結婚後は専業主婦となっていた。それはどこから見ても、まるで穴の見当たらない堅実な家庭だ。しばしば言われるのが聖子の生家である蒲池家は、久留米の大名に繋がる旧家であるし、母親も地元の農民とはいえ庄屋の出である。そして父親の職業は地方でなく、日本政府に直属する公務員だった。この家庭は、もそれを裏付ける経済的な点でも、まだまだ高度経済成長が始まったばかりの地元北九州・久留米では最上層ではないにしろ、余裕で中流以上の地位にあったと思われる。そうした家庭の中で、法子は蒲池家の長女ということになっているが、実際には8歳年長の兄がいるのみで、実質的には4人家族の末っ子だった。
経済的な問題点が特に見られない家庭で、家族で最も幼く、しかもその子が女の子であればなおさら、家族中の愛情、特に両親のものがその子に集中しやすい。法子の赤ちゃん時代は丸々と太っていてけっして器量の良い赤ちゃんでなかったが、出生間もない時期の器量などはあてにならないものであり、そんなことは両親にとって問題にならなかったろう。むしろ、丸々とした体形は乳児の可愛さを誘う有力な誘因のひとつであることは、既に述べた通りだ。また法子は出生時には難産のため仮死状態で生まれ、その後も小児喘息を患うなど、けっして健康優良児ではなかったが、両親にとっては、それゆえ尚更、自分たちの十全な保護のもとに置かなくてはならない子として、法子に注意を集中させることとなった。
さらに有利な点がもう一つ、家族内にあった。それは兄との年齢差である。法子の誕生時に兄はある程度、両親べったりの時期を既に脱しており、しかも同性の姉妹同士のようなライバル関係にならないだけに、法子が両親の愛情を独占に近い形で受けたとしても、兄との葛藤・軋轢は決して深刻なものにはならなかったろう。
家族内だけではなく、親族や地域の近隣の人々にとっても法子の位置は絶好だった。そもそも‟可愛い”という言葉は、人間同士、あるいは社会のヒエラルキー、階層にも深く関係した言葉でもある。それは皇室や王家の子どもたちであるプリンスやプリセスたちがが、本人たちの実際の器量とはほとんど関係もなく“可愛い”と持ち上げられる一方で、近所の農民や団地の家庭の子どもが、そのように呼ばれるのは、ごく限られた知り合いからのお世辞である場合に限られることを思い起こして頂ければ、明らかに上位階級の方が下層の人々よりは‟可愛い“に相応しいとみなされることが、納得いただけると思う。つまり周囲の“可愛い”はその子供を対象にするというだけでなく、同時に社会的地位を持つ両親への賛美でもあるのだ。
また、一方で、“可愛い”は、可愛いとされる対象の者と、”可愛い”と呼ぶものとの関係では、上下関係のエラルキーを前提とした、下の者に対する“上から目線”の言葉ともなる。“可愛い”と呼ぶものは“可愛い‟とされるものを自分の保護下、支配下にあるかのように意識的にも、無意識的にも見なすのが普通だし、一方で、‟可愛い‟とされた者は、‟可愛い‟と呼びかけるものを、自分より力のある者、階級の高いものとして、敬い、その代わりに保護を期待する。
周囲から一目置かれる堅実な家庭の末っ子で、なおかつ女の子という法子のポジションは、ここでも最大限の効力を発揮する。高位の社会集団に所属すると見なされながら、その社会集団内では低位にいるということが、外部からは憧れと同時に親しみやすさの対象と映るのだ(注4)。幼年時代の聖子が、家族内のみならず、親族内、そして地域のコミュニティに属する人に出会う度に‟法子ちゃん、可愛いわね”という言葉を結婚式でのカップルに対する紙吹雪のようにかけられれたであろうことは想像に難くない。さらに好要因がもう一つあった。法子の近所に住み病院を経営していたという叔母には自分の子どもがいなかったのである。
多くの子供たちの場合、“可愛い”と呼ばれる幸福な時代は、ごく幼い時期に限られる。成長に伴い、自分の持って生まれた資質(特に外見的な器量)や生まれ落ちた生家の社会的階層の限界に徐々に気づかされ、遂には“楽園”追放の時期を思春期までには迎えることになる。
だが、法子は別だ。出生当初は太っていて”ぶたまんじゅう”というありがたくないニックネームをもらった法子だったが、成長とともにすっきりとしまってゆき、美しい母親と知的な風貌をした父親から引き継いだ器量の良さを徐々に発揮し始める。とはいってもその容姿は‟美しい‟と呼ばれるにはクールさに欠け、いささかありきたりではあるのだが。だが、それこそ、この可愛いと呼ばれるのにうってつけの場所で成長することとなった幸運な少女に相応しいものであることが後ほど判明するだろう。そして、彼女は大きな挫折もなく成長を続け、外交的で活発な資質も開花させてゆくことで5才ころまでにはお転婆と呼ばれるような生命力に溢れた少女となり、ますます周囲を惹きつけてゆくことになるのだ。
もう誰もとめられないわ
走り出す 風の中
“わたしはわたしよ、あなたのものよ”
私たちは、後の80年代前半の聖子が、可愛い女性になりたい、としばしば言うことを聴くだろう。そして、多くの女性が今でも“可愛い”ということに憧れ、‟可愛くなりたい“あるいは‟可愛くありたい”と願っている。だが、可愛く“成る”、あるいは可愛く“ある”というのは厳密にはありえない。なぜなら‟可愛い‟が成立するのは、‟可愛い‟とされる対象よりも、あくまでその対象を外側から見る他者の反応の中にこそあるのだから、‟可愛い”を望むものが、それを自分の内部で主体的に作ったりできるものでない(注5)からだ。
つまり、‟私は可愛いと呼ばれるようになりたい‟が正確な言い方だ。それでも多くの女性は可愛くなりたいと願う。では、どうやって法子は、そして女性の多くは“可愛く”なることを実現するのだろうか?
私は可愛い、というとき、それは私は強い、私は美しいという場合とは、根本的に異なる。私は強いという時、自分の体の中に力が溢れていることは自分で感じることができる。自分が弱り、打ちひしがれている時に、自分が強いなどと認識する人はいないだろう。他者から君は強いといわれ、その認識を強化することはあるかもしれないが、体内の充実した力強さの認識そのものは自分で可能なのだ。
美しさは可愛いとは、かなり近接した概念であり、どちらも基本的には人の外観に対する概念ではあるが、両者には決定的な差がある。美しさには人が属する文化圏による違いがあるものの、同一文化圏の中では“美しさ”に対する比較的明確なの基準が確立されていて、しかも、その質的な面では、凡庸なものに対して隔絶したものである、という合意が成立している。そこで、“私は美しい”という人は他人に、それを指摘されなくとも、やはり自分でその認識は可能だ。
一方で可愛いという概念は、‟美しさ“のような凡庸からの隔絶ではなく、それと近接したものでありながら、また違った何かがあって好ましい印象を与えるということだから、その基準は曖昧で、複雑なニュアンスを持った概念だ。だから、同じ身体的な特徴が、ある人にとっては可愛いさになっても、別な人にそうならない、といったことも多い。
美しいは絶対的だが、可愛いは相対的なのである。そのため“可愛い”は常に他者からの確認を、‟可愛い‟と呼ばれる事を繰り返し必要とする。逆に言えば、”可愛い”くあるためには、他者への積極的働きかけ‐アピール‐が欠かせないのだ。
物心も未だつかず、自分と他人との区別も定かでない幼児期には”可愛い”と呼ばれることは、他者から保護されることの生暖かいまどろみ、両親に、そして周囲の大人たちの所有物になることで得られる安心感であったろう。
しかし、やがて幼い法子はまどろむだけでは我慢できず、自分の可愛さを積極的に求めるようになる。法子はこの自分に向けられる”可愛い”という言葉に通常の子ども以上に鋭く反応するのだ。それは、おそらく、法子の育った家庭の中で置かれた位置が、まだ物心をつくかつかないかの彼女の中に、“可愛い”という価値を絶対的なものとしたからだ。
ごく幼いころから彼女には、誰からも美しいと呼ばれた母親や、かなり年長で、学業優秀、その上、ハンサムな兄に対する強いコンプレックスを持ったためかもしれない。特に母親が持つ容姿との質的な違いは法子にとっては決定的なものだった。幼い頃から法子は自分の一重の目と比べて、二重のきれいな目を持つ母親を羨ましがり、母親に対し、”私の目と取り換えて!“と頼んでいたという。器量が悪いどころか、むしろ上々のはずの法子だが、一方で、自身の外見が母親の持つ”美しさ”とは別種なもの、つまり美しいという絶対的なものでなく、より凡庸に近いものであることとは確実に認識していたのだ。また、兄という親しい関係の男性が、年齢、器量、学力から来る家族内や近隣社会内での認知度で圧倒的な力量差を持っていた場合、幼い妹は同じ土俵で兄に対抗できようはずもない。そんな妹はひたすらその兄に好かれたいと思うのみだったろうし、兄以上に注目を集めたいと願うなら、今の自分が一番、注目を集められること、つまり可愛くあることでしかない。
いずれにせよ、法子の中で“可愛く”あることに対する強い執着が生まれたとしても不思議でない。
そこで法子は抜け目なく周囲の人々たちの反応を見て、そして感じる。彼らは可愛いねぇといいながら満面の微笑みを自分に向ける。そして、法子が、思わず自分が認められた嬉しさのあまり声を上げて笑うと、彼らの表情はさらに緩み“可愛い、可愛い”を繰り返すのだ。時には、笑い声の褒美に法子の大好きなお菓子やおもちゃをくれることもある。こうした反響を通じて法子は‟可愛い‟そのものを、まずは他者に現れる自分への反応として感じ、そして、次の段階では、それにある種のやり方で積極的に働きかけ‐アピールすることができることを学ぶのだ。
遠からず法子は、周囲の人々に満面の笑顔をふりまくことを覚えるだろう。その笑顔が周囲の人々を喜ばせ、ひいてはそれが自分にさらなる幸福感を与え、時にはそれだけでなく、実利的な利益さえもたらすことがあるのだ。そしてその際、軽く首を傾げればその効果をさらに増幅させることができる。
こうした”可愛いへの働きかけの効用”の発見は法子にとって決定的な啓示となる。それは家庭内のヒエラルキーでは最下位のはずの法子を一気に最上位にまで引き上げ、法子の欲求を実現させてしまう魔法の力だ。”可愛い”はもはや単なるまどろみの心地良さではなく、法子が自らの働きかけによって実現させることのできる生の可能性として、最初は漠然と、しかしある種の確信を伴って認識することとなる。いずれ、法子が聖子と変身していくにつれ、この認識は彼女の生の核心となるのだが、それはまだ後のことだ。そこに至る間、法子は‟可愛い‟と呼ばれる度に、”可愛いをアピールすることのできる様々な表情や仕草を身につけてゆくのだ。
こうした法子が身につけた表情や仕草を含めたそのもろもろの”可愛い”への働きかけの行為=アピールは、必然的に演技=パフォーマンス、あるいはジェスチャーに近いものとならざるを得ない。”可愛い”が法子の内部にない以上、それを法子の内的な感情=エモーションに基盤を置くことはできず、他者に対して‟可愛い”を成立させる、あるいは増幅させる効果を狙った手段とならざるえないからだ。
その後、法子が松田聖子としてアイドル歌手としてデビューする頃までには、仕草や表情だけでなく、身につける服装やメイクでそれらを補強することも学び、さらには、時と場合、対する相手に応じてそれらを様々に使い分け、変奏する術を一通り取得することになる。このことを指して人々は後年、聖子の‟可愛い‟を‟ぶりっ子‟と呼ぶことになるだろう(注6)。
今の段階で重要なのは次の点だ。つまり、こうした法子が身につけた様々な”可愛い‟くあるためのアピールは、成長のきわめて早い段階から、あまりに頻繁に行なわれ、しかも多大な効果を長期に渡ってあげ続けたため、法子には、それらが目的をもった意志的、意識的な行為とは自覚できず、”嬉しい“‟悲しい”といったエモーションの自然な発露の結果と区別がつかなくなる。
実際、法子はそうした彼女の”可愛い”行為=アピールが効果を上げた瞬間ほど、幸福感を感じ、嬉しく思える時は他にないのだ。そして、この“可愛い”を法子は自分の属性であるかのように見なし始めてゆくのだ(注7)。
しかし、”可愛い”は外部から与えられるものなので、法子は自分の内部にそれを見つけることは、もちろんできない。代わりに、どうしても‟可愛く‟ありたい法子は、‟可愛い‟という概念をささえる社会(あるいは人間関係)イデオロギーを受け容れることから始める。
既に述べたように‟可愛い”ということ自体には、自分自身を人間関係のヒエラルキーの中で比較下位に置くことを必然的に伴う。しかし60年近く前の、日本国内でも保守的な意識の強い九州で生まれ、女性である上に、実際に家庭内で圧倒的に幼かった法子にとって、何ら疑問や葛藤を伴うものではなかったろう。女である自分は年長の者に、そして男に従い、ついて行くものである。けっして出しゃばらず、つまり自己主張を強く持ってはならず、おしとやかであるべきだと法子は自分に言い聞かせる(注8)。笑ってしまうではないか。どれもこれも、後年の松田聖子にはまったく相応しくない。しかし、法子は、そして、おそらくは今の聖子でさえ、これらを本気で信じているのだ。
フェミニズム(当時はまだウーマンリブと言った)はデビュー当時の聖子を山口百恵が象徴した自立した女性像からの後退、反動と捉え、次に90年代に入るころにはその評価を正反対に逆転させ、したたかに男社会の中で自己実現をしていく女性として評価し直したわけだが、当の聖子は、少女時代に受け入れた保守的な考え方を何ら変えたわけではない。ただ、それは自分の性ではない、ということを聖子は既に悟っているが、少女時代の法子はそれに気づいていない、というだけだ。
もっとも、法子はこの自己抑制のイデオロギーを、彼女なりの生きるための処世術に置き換えて理解したようだ。大抵の事には自分を強く出すな、さっさと折れてしまって構わない。しかし、その代わり、どうしても必要なこと、欲しいものには妥協はしない、それは絶対に譲ってはいけないと。
聖子を聖子たらしめたもの、他にも数限りなくいたはずの“可愛い”少女たちとの道を分け隔てたもの、それは“可愛く”ありたいという彼女の強力な意志だ。外観や生育環境でのアドヴァンテージを持つことができたため、幸運にも‟楽園追放“を免れた女性が、その“可愛さ”を生存戦略のための道具として活用することは珍しい事ではない。
しかし、聖子にとっては、それ以上に積極的な意味を持つ。‟可愛くあること‟は聖子のアイデンディティとなり、遂には生の可能性そのものと呼んでいいものにさえなっていく。通常、人はそこまで“可愛い”ことにのみ入れ込むものではない。生きてゆくためには、それ以外の価値を見出し、身につけることがどうしても必要になるからだ。結局、多くの女性にとってさえ“可愛くあること”は人生の余得であるに過ぎないだろう、仮にその余得が決して少なくないものであるにしても。
だが、“可愛い”にうってつけの少女である法子は、“可愛い”自分を至高のものとして受け取る。可愛くない自分などとは考えることもできない、あってはならないものなのだ。だが、‟可愛い”は、母親の持つ美しさとは違って、そのまま自分自身の中に即時的に存在しうるものではないのだ。“可愛い”は自分の行為によって作り出さなくてはならない。だから法子は突き動かされるように、積極的にそれを追い求めてゆく。まるで他の価値など目に入らないかのように。
やがて、この強力すぎる”可愛くあること“への意志は、彼女にとって、当時最も身近にあった音楽‐歌謡曲‐を歌うことで、自分を表現することへの強い興味と意欲を幼い法子にかき立たせることになる。実際に80年代の雑誌を見ると、そこには小学一年生の法子が着物姿で親戚の結婚式で歌を披露する写真が掲載されていたし、数年前のNHK番組ミュージックポートレイトでも父親の仕事上の同僚の前で民謡の黒田節を披露したという逸話を披露している。ただ、歌謡曲や民謡を歌うことは、ピアノ演奏などのアカデミックな音楽教養として一般的に評価されるものでない。そのため法子の歌への執着は、単なる子供の遊びと見なされ、成長の機会が与えられないまま放置されてしまい、法子の生きることへの情熱のかけがえない対象となるには、今しばらく時を待たなくてはならない。
こうしたことから、思春期(=人間としての自己の確立期)以前の法子の様子は大まかに想像することができる。
富豪というほどではないにせよ家庭的にも物質的にも何一つ不足のない環境で、伸び伸びと育った活力に溢れた明るい少女。両親には従順で、反抗的なところはほとんど見られない。自分の”可愛さ”を自覚していると同時に、その‟可愛さ‟の維持のために、積極的なアピールが必要だということも承知していて、それを欠かすことはないように周囲には常に気を配っている。だがら、目立ちたがり屋という反発がないわけではないが、器量が良く、誰に対しても愛想は良く、親しみやすい少女ということで周囲から好かれ、同時に、甘え上手(注9)で、自分の要求を反発を避けながら通すことに長けているので、調子よく、少しばかりちゃっかりしたところもあるとも思われている。勉強はどうしても必要と観念しているので、一通りそつなくするが、決して熱心な方ではない。音楽が大好きだが、興味の対象は教養としての芸術音楽でなく、より親しみやすく、なによりも”可愛く”あることができるのに最適な歌謡曲だ。お洒落についての関心も既に芽生えているが、両親の手前、あまりそちらに情熱を傾けることには自制を働かせている。
この、さして強い特徴の強さを感じさせない、どこにもいそうな少女は、一方で、その内面には、ひ弱そうな外見とは裏腹の逞しい意志と情熱=エゴ(“可愛くありたい‟という強力な意志)を密かに持っている。ただ、この時点では、本人も含め、そのことには誰も気づいていない。それは法子自身が、自己をあまりに強く押し出すことは”可愛い‟を損なうことだと、習慣からほぼ無意識的に感じ取って自制を効かせてしまっていることもあるが、何よりもこの自己を発現していく方向性を未だ見出し得ていないからだ。この誰でもなく、どこにでもいそうな法子がどのように松田聖子を見出してゆくのだろうか。
(後編に続く)
-------------------------
注1: 日本語での可愛いは、通常、英語ではpretty,あるいはcuteと訳されることが多きが、実はそのニュアンスはかなり異なっていて、厳密には日本語の可愛いの訳語にはなりえない。今やアニメなどの日本発大衆文化の重要なエレメントとなった”可愛い”はKawaiiとして世界的に通じるようになっている。
注2: 可愛いという言葉は、人間だけのみならず、他の生物や無生物も対象にしているケースもとても多いが、ここでは取り上げない。そのほとんどの場合は人間を対象にした”可愛さ“の投影で説明がつくし、聖子論とはほとんど関係しないからだ。
注3:聖子のデビュー時のキャッチフレーズは”抱きしめたい、ミス・ソニー“だった。抱きしめたいというのは愛情表現で、近くで守ってあげたい、ということだ。
注4: 芸能人としての聖子が、実際には実年齢や芸能界のポジションから言えば、アイドルの女王ともいうべき地位がより相応しいにもかかわらず、今に至ってもファンからは依然として女王よりは低位である“姫”あるいは“プリンス”と呼ばれる事も同時に想起していただきたい。
注5:典型的な例として、もう初老オヤジである私が“可愛い”と呼ばれてしまったという先ほどの例を考えてみて欲しい。その時、私が何かを意図し、何らかの行動を起こした、ということでは全くないのだ。ただ、私は何かをやり損なった、というだけで、その時、私は若い女性社員に呼ばれるまでは、自分が可愛い、などとは全く認識できず、それは突然、外部からやってきたのである。つまり可愛いは私の内側でもなければ、私の行動にでもなく、ただ私の外側に存在している。もっとも、私の場合は可愛いに対し全くの無防備だったのに対し、法子の場合は、多くの経験を通じ、”可愛い”に自ら働きかける術を豊富に持っていたという違いは大きい。にもかかわらず、可愛いはあくまで外部にあるのであり、自己の内部にはない、という点では変わるところはない。
注6: 結論として、私は‟可愛い‟と‟ぶりっ子“とは本質的には同じものだと考えている。‟可愛い”はぶりっ子とならざる得ないのだ。この点は次回、さらに考察を深めてゆきたい。
注7: 結局のところ‟可愛い“は外部からの評価であり判断である以上、‟可愛くなりたい”ということは、自分より他者に自己認識の主導権を与えるということに他ならない。つまり“わたしはあなたのものよ”というわけだ。ただ、この表現は心情を表す詩的表現としてはありえても、実際には実現し得ないし、どこかで自己の再獲得=”わたしはわたしよ”が必須となる。やがて‟可愛い“の熱心な探求者となる松田聖子の逆説がここにあり、それが生涯のテーマとなるだろう。
注8: 81‐82年ごろ、聖子は将来の結婚について聞かれると、仕事は辞めると答え、同時にここに書いたような、まるで絵にかいたような保守的(いや、反動的と呼ぶべきか?)な結婚観を臆面もなく雑誌で述べていたことを覚えておいでだろうか?当時、私はこれを冗談か、雑誌インタビュー用の‟おしとやか”ぶりっ子程度に思っていたのだが、今になって思うと、聖子は本気でそう思っていたのだろう。
注9: 法子は3月生まれなので、もっぱら同学年の友人たちたちからは末っ子の妹のように見做されたらしい。これまた反発を避けながら、可愛いとされるには好都合な位置である。
1960年生まれ。
様々な音との出会いを求めて世界を彷徨い続けていますが、ふとした拍子に立ち戻るのは、ジョアン・ジルベルトと松田聖子、そしてエリック・ドルフィーの音の世界。聖ジュネで示された方法論を応用して聖子を理解し、語り尽くすのが夢。
プロフィール写真はJose Antonio Mendezの「ESCRIBE SOLO PARA ENAMORADOS/フィーリンの真実」レコードジャケットより。
Twitter ID:@bossacoubana

記事一覧はこちら