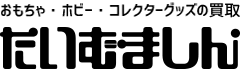松田聖子-In her life- 第一部(後編)<An Idol is Born アイドル誕生>
松田聖子 -In her life-
<第一部>
-後編-
An Idol is Born ~アイドル誕生~
‟何もかもめざめてく 新しい私
走り出した船はただ あたなへと続いている‟
法子の最も大切な生存原理、それは‟可愛く”あることだ。小学時代にはステュワーデス、今でいう飛行機会社のキャビン・アテンダントに憧れたようだが、これは当時の人気テレビ番組”アテンション、プリーズ”の影響だろう。あるいは、法子は既に幼い頃から国内飛行機便に何度も乗っていて、実際に彼女らを見ていたからかもしれない。いずれにせよ、法子が彼女らの”可愛い”制服姿に憧れたためであることは間違いない。
中学時代に入ると、テニス部に所属するが、それは、テニスをすること以上に”可愛い”テニスウエアに身を包んで見たかったからだし、志望高校を決めた大きな理由は、その高校の制服が洒落て可愛く思えたからだ。そして歌手になることを本気で志す前、法子の将来の夢は”可愛い”お嫁さんになることだった。
もちろん、こうした決断や希望の最大の理由が”可愛さ”にあるとは、法子自身は主観的にはそのように意識していなかったかもしれない。改まった場で問われれば、よりそれらしい理由をあれこれと挙げることになったろうし、本人もその建前を信じていたろう。しかし、それはむしろ”可愛く”あろうという、彼女にとっての原理が、、あまりにも広く、そして深く彼女を支配していて、彼女自身でさえ、それを前提に考えていることを意識さえできないほどだったと解釈すべきものなのだ。
法子が信愛女学院を進学先として決めた時、彼女はその洒落た可愛い制服を着る自分を想像した時点で既に彼女の心は決まっていたのである。クリスチャンの雰囲気に憧れたとか、成績が当時の彼女に丁度良いレヴェルだったとか、そうした一見、よりもっともそうな理由は、法子にとっては、実のところ、すべて後付けの合理化なのだ。
そうした少女時代の‟可愛いくある゛という法子の生存戦略は十分に効果を上げた。それどころか十分すぎるくらいだっただろう。家族の中では、両親、特に父親からは溺愛といっていいほど大切にされた。それを”甘やかされた”と言っていいかもしれない。親族や学校生活の中でも”可愛さ”は人間関係の潤滑剤となり、過重な負担からは免じられ、他者との深刻な軋轢を生むことなく、法子は明るくのびやかに生きていくことができた。それは意地の悪い見方をすれば、お気楽で安逸な生活と言えるものだったろう。後になって二十歳の聖子は自分の子供時代を回想して言っている。“根性という言葉と全く縁のない子供でした“ピアノを幼稚園の時に買ってもらい、習ったけれどもちゃんと弾けるまでにはならなかった、泳ぎたいと思ったが未だにカナヅチ、英語も英検三級まで行ったけど、それ以上進めなくなってしまった(ただし、その後、30近くになって英語をきちんと習得したのご存知の通り)と挙げた上で、“昔から負けず嫌いのくせに途中であきらめてしまう”と結んでいる。
根性がないというのは、その人が持つ目標に対して、それを成し遂げるための気力や熱意が不十分という意味だ。多くの場合、その原因はその人の資質に求めることになってしまいがちだが、実の問題は、その人が達成すべき目標に対して意義や利得を見出し得ていないために、十分な意欲を持つことができないことにある。
元々音楽に強い興味を示していた法子のピアノ学習が続かなかったとすれば、それは、ピアノ学習を通して法子が実際に得られたものと、法子が音楽を通じて得ようとしていたもの、望んでいたものとの間には大きなずれがあり、そのためピアノ学習を継続する為に必要な忍耐を維持するほどの強い動機付けが持てなかったということを表す。泳げなかったことも、英語の学習も、そのどちらもが、その場の負担に耐えてまで、法子が全力を尽くして獲得しなくてはならないほどの意味を感じなかったからだ。
だが、そんなところで何の問題があったろう。別に法子自身も、そして家族も、彼女が音楽やスポーツ、あるいは教養で生きていく必要などは感じていなかったのだ。ただこのまま法子が“可愛い”まま成長をしてゆき、やがては経済力のある配偶者を得て、‟可愛いお嫁さん‟になり、安定した家庭を築く、それこそが望みだったのだから。
といっても、法子は子供時代から、人一倍、活発な生命力をもった少女であったので、保守的で拘束の強い中産階級イデオロギーには収まりきらない生命力を発散させる突破口を見つける必要が出てくる。
こうした場合、一般的にはその対象となるのは、勉学、スポーツ、音楽の三つのいずれか。この中で、最も人気がないのは、当たり前だが勉学だ。スポーツや音楽が主に肉体的・感覚的なものに訴えるのに対し、勉学にはそれなりの修練が必須となる知力に訴える必要があるため、子どもには取りつき難いからだ。それでも実際には勉学に力を注ぐ子供が多いのは、親の強い指導があるためだ。だが、法子の場合は、幸運と言っていいのかはわからないが、かなり年上の、しかも勉学に秀でた兄が勉学への家族からのプレッシャーは彼が一手に引き受けてくれたので、法子へのものは大幅に軽減されてしまい、勉学に必要以上に身を入れたりはしない。
一方で、スポーツは50年前の女性にとっては、通常はよほどの事情がない限り、片手間の趣味としてはともかく、本格的に取り組むものとしてはなりえない。戦後とはいえ、はまだまだ女性にとってのスポーツの価値はそう深くは認識されていない時代だったのだ。何よりもスポーツの出来る活発な少女像は聖子の目指すおしとやかな可愛い少女とは違うのだ(注1)。既に述べたように、中学時代、法子がテニス部に所属したのは、これはテニスウエアという”可愛い”装いに憧れたのであって、テニスという肉体運動自体に打ち込みたかったわけではない。
残るは音楽だが、幼い頃より音楽に強い興味を示した法子に両親はピアノを買い与え、それを習う機会が与えたが、実際に法子が最も惹かれたのは、音楽そのものをピアノという道具を使って奏で、音と向かい合うこと以上に、自分の声で歌を歌うことで自分の内部に潜む願望を自分の声を通じて表現すること、その結果として他者に働きかけることだった。
これは法子が音楽を通じて音によって構成される感覚的で抽象的な美を感じとる喜びを得るという以上に、音楽が持つ具体的なイメージの喚起力と、そして音、特に声と身振りによるコミュニケーション能力といった具体的な効用により魅力を感じていたということを表す。物心がつくかつかないころから、ひたすら可愛くありたいと願い、それを実現させようとしてきた法子にとっては、それは当然の帰結だったろう。歌うという表現行為自体が、他者の感情に訴えることを目的とするという点で、あの“可愛いく”あるための行為=アピールとほぼ同じものに思われたはずだから。
そして、法子がテレビの中で、楽し気に歌い、演じている歌手や役者の中に、彼女の日頃の行為と同質なものを感じ、共感から憧れるようになるのもまた、あまりに自然なことだったろう。後に聖子はテレビ番組の中で、由紀さおりの”生きがい“を人生で最初の大切な曲として挙げて、”なんて美しい声だと感激して、初めてレコードを買ってもらい、何度も何度も聞いて歌っていた”と語っている。この”生きがい”の発表が1970年、まだ法子が8才の時だ(注2)。そして、歌うことは、彼女が普段、身の回りの特定の少人数に対して彼女一人に行う”可愛い”アピール行為より、はるかに効率的に、広範囲の人々に“可愛さ”をアピールしやすいものだったし、同時に、普段は“可愛い”くあるために無意識に抑えつけていることの多い、法子の活発な内面を解き放つ突破口でもあったのである。
結局、ピアノ学習は短期間しか続かなかったが、音の持つ美そのものへの純粋な志向よりも音楽の持つ具体的コミュニ―ケーション能力を好む傾向は、法子、そして聖子となった後の音楽的キャリアの中でも一貫して変わらず、現在に至ることとなる。
80年代の全盛期聖子の音楽をよく聞くものなら誰も、聖子の歌声にはクラッシックやジャズのような芸術音楽の影響は微塵も見られず、といって、ビートルズに代表される洋楽ロックや、その影響を受けたニューミュージックの影でさえ非常に薄い事に気がつくだろう(注3)。その声の根っこにあるのは由紀さおりや黛ジュン、そして天地真理・南沙織・小柳ルミ子、さらには演歌まで含む60年代後半から70年代初期の歌謡曲であることは明白だ。
つまり法子、そして後の聖子が一貫して好むのは、音楽として抽象度の高い芸術音楽よりは、大衆音楽なのであり、その大衆音楽の中では、アーティスティックな上昇の強いニューミュージックよりは、より芸能的なエンターテイメントの傾向の強い歌謡曲なのだ。
一般的には最初のアイドル歌手とされるのは1970年にソニーからデビューした聖子の先輩となる南沙織だと言われる。もっとも、彼女が最初の、あるいはアイドル第一号だというのは、彼女のプロデューサーで、かつ自己顕示欲の塊であり、聖子の天敵である酒井政利の自画自賛から出たものであり、実際には、割り引いて考えるべきだ。同時期にはやはり当初はアイドル的人気を博した小柳ルミ子や天地真理がいた。それ以前にも、十代で大人気になった少女歌手というなら既に50年代からひばり、チエミ、いずみの三人娘が圧倒的だったし、60年代を通じ弘田三枝子を始め、今のアイドル的な人気を持った少女歌手はいくらでもいたのだ。歌手に限らねば、吉永小百合、岡崎友紀を始めにそんな例はもっとあったろう。ただ南沙織のそれ以前の少女歌手との違いは、彼女の音楽が彼女の同世代の思春期真っ只中の10代の少年・少女に焦点を絞ったものだったということだ。
何を当たり前のことを…と私より年代が下の方々には思われるだろうが、実はそれ以前の歌手は、時代的にまだ文化の世代的細分化がそれほど進んでいなかったこともあり、10代の若い歌手といってもティーンエイジャーの若い世代のみをターゲットにした音楽活動をしていたわけではないのだ。
当時の歌手たちの想定していたファン層は‟お茶の間‟、あくまで若者は家庭の一員として存在する、老いも若きも一同に集った憩いの場としての“幻想共同体”だった。これは、同時代の小柳ルミ子のヒット曲、瀬戸の花嫁が日本情緒溢れた国民的、つまり全世代的ヒットだったことに明確に表れている。また天地真理はデビュー時の実年齢が案外と高かった(既に19才を過ぎたほぼ二十歳)だかったこともあり、やはりファン層を広めに想定せざる得なかった。
一方、南沙織は、お茶の間=家庭から距離を置いた若者だけの空間にぴったりとはまるような、青く、爽やかさに溢れた可愛らしさを歌った(注4)。これは日本の大衆音楽の主流(=つまり歌謡曲)が、この頃までには確固たるものになっていった若者文化を積極的に取り込みだし、1970年以降は、未だ経済的には自立ができていないティーンエイジャーまでを、お茶の間とは別個のマーケットとして認めて対象にし始めたということを表す。そして、南沙織以降のアイドルはすべて‐もちろん10年後にデビューすることになる松田聖子も‐それに倣った。
それまではあくまで家庭内やごく親しい個人的な交遊関係の中にのみ存在した“可愛い‟という価値観が、この段階で初めて、経済的なマーケッティングの対象となることで、現代資本主義=大衆社会の中の文化事象として取りこまれたことを意味する。
そして、この社会文化事象としての“可愛い‟を体現した大衆メディアこそ、私たちが現在、普通に考えるアイドルであり、この事象は、ちょうど、法子の物心がついてから思春期までの時期にあたる1970年代を通して、マスメディアが媒介する音楽と視覚的イメージを通じて一般的で確固たるものとして確立される。
戦後社会、特に法子が生まれてから育った1960‐1970年代は、日本経済が右肩上がりだったこともあり、日本人全体が社会階級の上昇志向を持ち得た、その面では幸福な時代だったと言っていいと思うが、法子自身も彼女の家庭も例外ではなかった。いや、それどころか、そうした社会的上昇志向-これをわかりやすく野心と呼んでもいいだろう-は人一倍、強く持っていた。
つまり、法子身は、おっとりしたお嬢さんには収まりきらない、もっと野心に燃えたギラギラした面を持っていたのだ。1980年代のアイドル時代にはそうしたギラギラした上昇志向をあまり表面に出さないようにしていたが、1990年代のアメリカ進出時には、それを包み隠さずに表に出すようになり、聖子は変わってしまった、肉食聖子なんて…と昔からのファンを大いに嘆かせた(?)わけだが、よくよく考えてみれば、それも聖子が間違いなく持っていた一面であり、何もアメリカ被れをした90年代になって、突然、変わったわけではない。むしろ、80年代はもちろん、まだ歌手になっていない法子だったころからずっと持ち合わせていたものと考えるべきものだ(注5) 。
法子が貧しい家庭の出身ならともかく、一応、地方のお嬢さんであるだけに、野心が強いということは意外に思えるかもしれない。しかし、社会的上昇志向と呼ぼうが、野心と言い換えようが、これらの言葉をよりわかりやすく、さらに口当たりの良く言えば、それは‟夢‟となる。
夢とは何も下層階級の独占物でなく、日本社会のあらゆる階層、階級の若者たちに社会から強制される強迫概念のひとつだ。それが、どのように家庭で、学校で、そして社会から、絶え間なくけしかけられるかは、テレビや雑誌、J-POPの歌詞の中に夢という言葉がどれだけ溢れかえっているかを見れば明らかだろう。そして、法子の家庭のような中層よりは上位に属する家庭では、たとえ法子が女の子であったために抑制的であったとしても、両親の子供に対する期待という形で上昇志向=野心がしっかりと法子の心に刻まれていたことだろう。
法子の家庭自体は福岡で長く続いた生え抜きと言っていい家庭だったが、実は東京との繋がりがかなり強い。地方では東京に出たり、関係を持つことが、そのまま社会階級の上昇に結びつくと無意識的に刷り込まれるが、地元との繋がりが強固な農民や地元企業のサラリーマンでもない、中央省庁である厚生省の役人だった父親の娘である法子もそうした思い込みを素直に、それも通常以上に強く刷り込まれたろう。実際には父親は、東京への出張も頻繁に行っていたし、法子も幼い頃から、既に東京に出ている親戚を頼って何度も東京に旅した経験を持っている。このため東京への親近感が人一倍強かっただろうことは、もう幼い頃から久留米弁とともに標準語で話し、使い分けができたことでも容易に想像がつく。
東京への憧れは、社会階級上昇志向に容易に転嫁するので、これをもって、聖子ファンは、聖子の地方出身者のド根性、としばしば言うのだが(注6)、聖子にとってはそれだけでない、もっと重要な要因があった。それは、彼女の‟可愛く‟ありたいという人一倍強い彼女の意志であり、それこそが、何よりも彼女の強い上昇志向=野心を作り上げたとみるべきなのだ。
‟可愛い‟くあることは他者からの承認なしには決して成り立たず、そして不断の確認を必要とする。法子は”可愛く”あることを努力し、それが成功を収め、まずは彼女の家族を虜にする。そこで得た自信は、やがてはアピールの範囲を近親の親族の間に、そして彼女が普段、触れ合う交友関係の中に拡がるだろう。
しかし、それだけでは、その効果は比較的少数の人々の間に留まった、個々の人間関係間の反響でしかないため、いずれは法子の‟可愛くあること‟の欲求を満たせなくなってくる。もし勉強ができたり、あるいはスポーツに秀でることができるなら、それは子供にとって最も身近にある家庭外の社会=学校や地域で公式に認められるし、それは将来の社会的地位の保証につながることにも直結するだろう。しかし、そこでは可愛くあっても、それで進学ができるわけではなければ、それが人間的な評価にも必ずしも結びつかない。しかも法子は家族以外の人間からの‟可愛い‟という評価はあてにならないことを、様々な機会で思い知らされている。小学生時代からの初恋は、その憧れの幼馴染の気持ちを遂に掴むことなく終わっている。また、自分の可愛さからクラスみんなに好かれているという自信から、クラス委員に立候補したが、実際には誰からも投票されなかったという屈辱もあった(注7)。
可愛くあることは、手応えの感じにくい不安定であり、何も保証はしないのだ。”可愛く”あることが実現可能とするものは、せいぜい、少女にはまだ漠然としたイメージでしか考えられない将来の‟可愛いお嫁さん‟になることでしかないだろう。それであればこそ、法子はますます‟可愛く‟あることを、もっと多くの人達に、もっと広範囲に訴えなくてはならないと思うようになるだろう。‟可愛さ‟の評価の量的拡大、これこそが彼女に確実な手応えをもたらし、法子の社会的上昇志向=野心の実現を可能なものにするように思われるからだ。
こうした法子の欲求を完全に満たせるもの、それがアイドル歌手であることはもはや言を待たないだろう。‟可愛く”あることが歌うことに結び付き、歌うことが‟可愛いく”あることを広く、強く保証し、さらには社会的な地位をつくることにさえ結びつく。これこそが、後の聖子が夢と呼ぶものだ。なるほど、これほど聖子、いや法子に適した夢が他にあるだろうか?それまで、何事にも中途半端な取り組みしかできず、周囲に甘えるだけだった法子が遂に自分で実現すべき夢を見つけたのだ。
‟いけないことだって知っているわ
それでも愛は急に止まれない‟
一般的に知られる松田聖子伝説によれば、彼女の歌手になるきっかけは高校2年生の時に、ソニーの主催するミスセブンティーンのオーディションに、憧れの郷ひろみに会えたら(あるいは優勝者に与えられる懸賞としてのアメリカ西海岸のディズニーランド旅行をしたかったから)(注8)という理由で、両親に内緒で応募、九州大会で優勝したことだ。だが、その後は、家庭と学校の反対で全国大会出場を断念、しかし、その時の歌声のテープをたまたまソニー本社の若松宗雄氏が聞いたことから、歌手への道が開かれ…云々のサクセスストーリーはファンなら誰もが知っているだろう。
この話を聞くと、ポピュラー音楽ファンには有名なもう一つの逸話を連想されるだろう。それは”元祖イパネマの娘”アストラッド・ジルベルトのデビューにつてのものだ。”ボサノヴァの神様”ジョアン・ジルベルトのアメリカデビュー時に、当時、新婚で“台所で鼻歌しか歌ったことのない全くのド素人”アストラッドが、たまたま英語が出来たこと(一方で、気難しい夫のジョアンは英語で歌うことを拒否)、そして声質も容姿も可憐で若かったことでプロデューサーに白羽の矢を立てられて、イパネマの娘でのリードヴォーカルを任された。そして、その曲がビートルズを蹴落として、全米No.1ヒットとなり、一躍、夫をも凌ぐ大スターが誕生してしまった、というものだ。
この聖子とアストラッドのふたつのどちら逸話にも、伝説には避けがたい事実の脚色と誇張が少なからず存在する。アストラッドは、実はもともとプロ歌手志望で全くの素人ではなく、結婚前から夫のジョアンの指導による個人レッスンをずっと受けており、既にブラジル時代にジョアンの伴奏でコンサート出演も経験済みだった。そして夫のレコーディングを自分のチャンスとして逃がさないように、夫を通じてプロデューサーに猛烈な売り込みをかけていたという(注9)。
聖子も、歌手になりたいというのは漠然とした希望に過ぎず、ごく気軽に何気に応募した、と語られるのだが、実は法子がプロのアイドル歌手になるためにオーディションに応募したのはなにもこれが初めてではなかったのだ。この一年ほど前の高校入学直後に、まずはテイチクの新人オーディション、次にホリプロのスカウトキャラバンに密かに応募していて、どちらも一次審査は通過しており、特にポリプロのオーディションでは地区大会の最終予選まで残れていた。依然として、まだ両親には、応募を依然として秘密にしていたが、ミスセブンティーンへの応募も、本人としてはそれなりの手応えを感じた上での3度目の挑戦、つまり、歌手になるという希望を実現させるための本気の試みだったと考えるべきものなのだ。
法子の幼い頃からの漠然とした芸能界への憧れが、耐えがたいほどの熱を帯びだしたのは、異性への関心が深まり、同時に自分の可愛いさに自信と自覚を深めた中学時代からだ。女性の”可愛いさ”は思春期以降は、急速に異性に対する恋愛アピールという側面を強くなるが、まだ10代前半では特定個人との本格的な恋愛交際が厳しく制限されるだけに、むしろ‟可愛くある‟アピールの対象は特定の人間でなく、より広い範囲の異性に求めがちになるだろう。‟可愛さ‟を人一倍、熱烈に求める法子はもはや、家族や身の回りのごく限られた狭い交際空間の中だけにの‟可愛さ‟ではもう我慢ができない。
そして、これらが理想的に実現できるものアイドル歌手なのだから、法子の歌手への憧れが日増しに強くなっていくのはもう避けられなかった。当時、法子は夢中になっていた郷ひろみのコンサートに行くのみでは飽き足らず、友達と芸能人ごっこに興じて、さかんにカセットに自分の歌を録音したり、アイドルを真似たポートレイト写真を撮ったりし始めている。こうした“ごっこ”遊びは度重なるにつれ、法子の熱もますますエスカレートしてゆき、ほどなく、もう後戻りが聞かない地点‐現実性の無いところに自分の行動によって可能性を作り出そうとする決定的な一歩‐にまで法子を運んでゆく。
中学を卒業して、高校入学までの春休みのある日、法子は数日前に見つけていた雑誌の中のレコード会社主催の歌手オーディションの小さな広告記事の切り抜きを取り出す。この数日間、寝ても覚めてもこの記事が法子の頭から離れなくなってしまってた。もはや彼女は自分の気持ちを、溢れ出すような憧れを、未来へと真っすぐに続く輝く一本の直線から目を逸らすことはできない。
法子は机の引き出しの中のポートレイト写真を幾つか手に取り、その中からとっておきと思われるのを選び出す。‟大丈夫。自分で言うのもなんだけど可愛く映っているわ‟ 次には、録りだめをしていた曲の中から自分に最も合ったと思われるものが入ったカセットテープをラジカセでもう一度、聞いてみる。OK, これで間違いない。そして夢中で申込書を作り、そこに自分の名前を書き入れると、雑誌に書かれている宛先の住所を封筒に書き込み、最後にテープと写真を丁寧に入れてきっちりと封をした。部屋から出る時、両親はいないのはわかっているし、見張られているわけもないのに、なぜか周りを見回して誰もいないことを確かめてほっとする。思い切り切り玄関のドアを開けて、外に飛び出すと、ちょっぴりまだ肌寒い初春の日差しが法子を真正面から照り付けた。眩しい。たまらず、急ぎ足で街角のポストに息を弾ませてたどり着くと、そのまま、すぐ封筒を投函しようとしたが、封筒がポストに吸い込まれる直前、一瞬、手と息がそこで凍り付いた。‟大丈夫、心配することなんかないわ。どうせ、オーディションに通るなんてこと、ありっこないから、これはただのお遊び‟。そう自分に言い聞かせて、固まった指先を無理に開くようにして封筒を手から放した。
カセットと写真をつつんだ封筒がポストにカタンと落ちた音が聞こえた時、もう一人の法子が心の底でこう囁いていたことを彼女は気づいていただろうか?でも、もしオーディションに通っってしまったら? その時は、私は歌手になる。絶対に諦めない。‟走り出した愛はただ、貴方へと続いている”のだ。
法子はほとんど両親に反抗などをしたことのない娘だった。実際、そんなことをする理由も必要もなかった。法子はただ可愛く成りたかったし、そうあるためには自分を強く出して生意気になってしまってはいけない。欲しいものがあれば、うまく甘えて、喜ばせてあげる方がよほど得策だ。両親もそんな風に可愛く育った法子に満足していた。反抗なんて意味のない愚行にしか彼女には思えなかったろう。
ところが、両親、特に父親が娘に求める可愛さと娘が望む可愛さには実はある違いがあった。父親は法子の可愛さがあくまで家族やごく近親な関係の中に、せいぜい、やがては娘の夫になる将来の恋人までに留まることしか望まなかった。実際、法子の可愛さがそうした狭い範囲に留まる限りは何の問題もなかった。しかし、法子がその範囲をもっともっと大きく、遠くへ遠くへと拡げようとした時に、ふたりの齟齬は決定的になったのだった。
なぜ、父親は強硬に法子の芸能界入りに反対したのだろうか。非常に堅実な家庭とキャリアを築いてきた男として、父親として、歌手のような‟浮ついた‟、カタギの者が行うものでない、要するにヤクザな世界に自分の娘が飛び込む事など許せない、そもそも世間に対し、みっともないではないか、そんな考えがまず頭に浮かんだことは間違いないだろう。もちろんそうした考えの基になったのは、雑誌や巷の噂でからかい半分の悪意で描かれる、芸能界なんて道徳の乱れたものが集まる汚れた世界であるという今に至るまで世間に残る根強い偏見だ。まだ子供だった法子も親の価値観も偏見も、そのまま自分のものとしていたから、当初はそれに怯み、躊躇することもあったろう。しかし、偏見は事実にも経験にも基づかないものであるから、芸能界に法子を熱心に誘ってくれた若松プロデューサーのような誠実な人間と触れ合うことができれば、それはやがてそれは解消するだろう。
父親の反対はもっと根の深いものだ。父親は法子が目指す可愛さの本質をほぼ直感的に察していたのである。可愛さというのは法子の中にあるものではない、それはその外にあるものだ。だからこそ、よほど法子がしっかりしていない限り、得体の知れない外部の誰かに自分を容易に譲り渡してしまうことで、愛する娘が、自分の手の届かない彼方で、自分を見失ってもみくちゃにされた挙句、堕落し、深く傷ついてしまう、それこそが父親が真に懼れ、嫌悪したことなのだ。もし、法子の可愛さの範囲がとても狭く、父親の手の届く範囲なら、それをコントロールすることで見守ることも可能だろう。だが芸能界に入って不特定多数の人々にまで可愛さを訴えることが必要になったら…もはや、父親はもちろん、守れるものなど誰もいないだろう。
結果から言えば、父親のこの心配は遠からず半分的中することになる。松田聖子となってデビューして以来、聖子はアイドルとして大成功した代償として、不特定多数の大衆という顔の見えない他者に思い切り翻弄され、幾度も長期に渡って自分を見失う危機に見舞われるからだ。
しかし、聖子はほぼ自分自身の独力で自分を守りきり、それを乗り切って現在に至っている。結果的には娘は父親が全く予期しなかった強さを持っていたのだ。で、当時の法子は、そんな父親の心配を理解していたろうか?おそらくは分かっていなかったし、近い将来に彼女を待ち受けるこうした危機など予見さえできていなかったろう。
ただ、彼女は単純に考えていたはずだ。‟大丈夫、何とかなるはずよ。もし、失敗したら?その時は、久留米に戻ればいい。父も家族も私を受け入れてくれるはずだ。そして私は今まで通りの可愛い娘に戻ればいいのだ。そして可愛いお嫁さんになる。今と何ら変わらないわ‟。
もちろん運命はそんなことを許してくれなかった。法子は聖子となり、もはや法子には戻れない。
(第二部に続く-執筆中です-)
(前編はこちらへ)
-------------------------
注1: 聖子は泳げないカナヅチであるし、80年代まではよくあった芸能人の運動大会で華々しい活躍ができたわけではないので、一般的には運動能力が高い、というイメージは全くないかもしれない。だが、本来は運動好きで、その方面の才能もあったのではないかと私は思っている。というのは、リズム感のいい人間は運動もできるものであるし、実際、ステージで見せる聖子の一瞬の動きの切れ味などはなかなかのものがあるからだ。聖子があまり運動を得意としなかったとすれば、それは本文にあるように女性は運動などできなくて良い、おしとやかの方が良い、という刷り込みからくる自己抑制があったためだと思う。実際、私の子ども時代には、運動ができないことを装ううちに本当に運動が不器用になったとしか思えない女性がたくさんいた。なお、私は聖子とはもし同じ中・高校だったなら学年こそ違え、同時期に先輩・後輩として学校に通えた年齢で、聖子とは同世代と言ってよい。
注2: 余談になるが、由紀さおりの当時の声の影響力は私たちが思う以上に大きかったのかもしれない。というのは個人的な話で恐縮だが、私が物心ついて最も印象的だった最初の曲が、由紀さおりの前年発表の“夜明けのスキャット”だったからだ。聖子と同じように何と美しい声だと思った。
注3:洋楽センスがあると言われた聖子だが、それは彼女のリズムセンスとか声質からきているもので、彼女の音楽的バックグランドとは別物だ。私は聖子にとっての本格的な洋楽との出会いとは、歌手になって以後、レッツゴーヤングで当時の欧米ヒットポップスを歌ったり、オリジナル曲が少ないためにコンサートで歌う必要のあった洋楽を勉強してから始まったのだと思っている。私たち以上の世代の洋楽派には(それは私を含めて)避けがたい優越感を、特に歌謡曲に対して持っている。そういった優越感は妙な自意識となって、歌にも必ず現れるもので、それはデビュー前には完全な洋楽派だったユーミンとか森高千里にはっきりと感じ取れる。一方で、良くも悪くも聖子の歌にはそれが全くない。私が聖子を全く洋楽派と思えない最大の理由だ。実は私は、聖子は洋楽どころかユーミンのようなシティポップス派のニューミュージックにもデビュー前には大きな関心がなかったのではと思っている。
‟人ごみの中で変わって行く私を
あなたは遠くでときどきしかって‟
ひたすら東京にでていくことで、自己実現を図ろうと考えている少女にこうした年生活者の感傷は無縁だったと思うのだ。
注4:南沙織の持っていた新しい資質、それはアンチ歌謡曲としてのニューミュージックに対する親和性といっていいと思う。それを可能にしたのは何といっても彼女の声質だ。きっちりとしたプロの発声を身につけた当時のプロ歌手としての正統派の声だった小柳ルミ子、クラッシク的素養があり歌のお姉さん的だった天地真理に比べると、南沙織のそれは少女の生の地声により近く、やや硬質な初々しい爽やかさに溢れていた。もちろん、聖子の初期の歌声は、この南沙織を引き継いでいる。
注5:子供時代に不十分なものに終わったとはいえ、法子は英語学習に興味を持っていた。これは法子が漠然としたものだったとはいえ何らかの社会的上昇志向を養っていたことを表す。英語は日本社会においては都会的な上層社会階級の記号だからだ。
注6: おそらく、一般的に地方というべきでなく、法子の育った久留米という土地の特殊性が何らかの少なからぬ影響があったと思うが、私は久留米に行ったことがなく、この点は何とも言えない。一般的に言えば、久留米は農村でなく、そして福岡の近郊都市である以上に工業都市であり、そのため、半世紀前であっても久留米の持つ文化特性は東京の文化に親和性があったと想像できる。久留米は聖子と同時代に大活躍したチェッカーズも生んでおり、そこに何らかの関連もあるはずだ。
注7: 聖子デビュー直後に、ぶりっ子ブームの反動としての同世代女性からの激しい反発があったが、その萌芽がこの事件なのだろうか?だが、法子はこれに諦めず、次回のクラス委員選挙では無事当選を果たしたという。その間に何があったのか、興味深いところだが、その辺りの事情は不明だ。
注8: 確か80年代前半のアイドル時代には‟郷ひろみに憧れて‟となっていたが、最初の結婚後は‟ディズニーランドに行きたくて‟と書き直された。どちらが理由だったとしても大きな違いはない。本当の心からの理由は‟何とか歌手になる道筋をつけたい”ということだから。郷ひろみやディズニーランドは、自分の躊躇や予想される家族からの猛反発に対する表向きのアリバイでしかない。
注9:アストラッドはこのデビューレコーディングの時、既にジョアンとの間に子どもがひとりいた。つまり彼女こそ元祖ママドルである。表向きの可憐さの裏に隠し持ったしたたかさ、という点でぶりっ子の先駆者とも言っていいだろう。なお、聖子は1983年夏のコンサートツアー、アン・ドゥ・トロワでジャズスタンダードのFly me to the moonとThe shadow of your smileの2曲をアストラッドと非常によく似た(と言うか、そっくり真似た)ボサノヴァ編曲で歌っている。聖子の音楽スタッフの中にも聖子とアストラッドに共通するものがあることを認識していた人がいたのだ。
1960年生まれ。
様々な音との出会いを求めて世界を彷徨い続けていますが、ふとした拍子に立ち戻るのは、ジョアン・ジルベルトと松田聖子、そしてエリック・ドルフィーの音の世界。聖ジュネで示された方法論を応用して聖子を理解し、語り尽くすのが夢。
プロフィール写真はJose Antonio Mendezの「ESCRIBE SOLO PARA ENAMORADOS/フィーリンの真実」レコードジャケットより。
Twitter ID:@bossacoubana

記事一覧はこちら