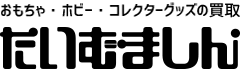『いちご畑のホールデン-聖子幻想-』松田聖子の極私的なポートレート
私が初めて聖子のコンサートに行ったのは1982年のことだ。その時「当時11才の家庭教師先の女の子を連れて行った」というのは本当にあったことだ。もちろん以下は創作である・・・。
--------------------------------
”いちご畑のホールデン” -聖子幻想-
-1-
僕が聖子のコンサートに初めて行った事を話すとなると、みんなはそのコンサートはどこで開かれたのかとか、聖子はどんな衣装だったのか、どんな曲を歌ったのか、誰と一緒に行ったのか、そんな事を根ほり葉ほり知りたがるかもしれない。でも、ハッキリ言って、その手の話はしたくても出来ないんだな。だって、もうずっと前のことで、本当のこと言って、細かい事は忘れちゃったし、覚えていることだってもうハッキリしない。僕はとんでもなく目が悪いのだけど、そんな僕がメガネを外した裸眼で通りの向こう側に聖子を見たとしよう。でも、実際に目に映るのは目鼻立ちもはっきりしない、辛うじて背格好や服装の色から女性とわかるという程度のもの。その娘が聖子だってわかるとすれば、それはその娘が聖子だってことをそもそも知っていて、あの聖子カットの髪型とか黄色のミニドレスとか、案外と長い首からむき出しの肩のラインとかの見当を勝手につけているからにであって、実際の聖子はもう聖子カットをバッサリと切ってしまった後かもしれないし、服装だってひよこドレスじゃなくて、同じ黄色でもバルコニーのパンツルックかもしれない。これじゃあ、好きだよ、なんて本当には叫べないはずだろう。つまり、これから僕が話す事は、実はこじつけの法螺話かも、ってことを承知していて欲しいってことさ。僕はすごいウソつきなんだ、自分でも感心するほどにね。
10月になったというのに、妙に蒸し暑い日だった。そのせいで僕はすっかりへたっちまっていたんだけど、それでも律儀に、午後六時にいつも通りに沙也加ちゃんの家を訪ねたわけだ。もちろん、この沙也加という名前は、僕が勝手に決めたものであって彼女の本名ではない。沙也加ちゃんはまだ11才のかなり可愛い、その上、いいとこのお嬢さん、僕はそんな彼女の算数と理科の家庭教師をして、学生時代の小遣いを稼いでいたというわけさ。
どう見ても将来の僕には絶対に縁がありそうもない、瀟洒な高級住宅街の一戸建ての家に着くと、呼び鈴を鳴らして、年配の家政婦さんに門を開けてもった。ずっしりとした、これだけで僕の住んでいたアパートの全部を買えるんじゃないかと思えるような豪勢なドアを開けて家の中に入ると、なんとそこには沙也加ちゃんのママが珍しくも立っていた。
彼女がどんな仕事をしていたのか詳しいことは知らないけど、僕が来る頃に戻っていたことなんか、それまでほとんどなかったんだけどね。この沙也加ちゃんのママ、仮に法子さんとでもしておこうか、おそらく、まだ三十代半ば、いや四十前なのかな、ただ、それでも、僕の同級生たちにも全然、負けないぐらい若々しくて、色白の、たいていの男がこんな人なら一生に一度くらいは食事を一緒にしたいっと夢見てしまうに違いないほどの魅力的な容姿なんだ。
そんな人が自宅だというのに、ロングヘアのほっそりした体を肩のラインが丸出しの黒いドレスで身を包んで、メイクも隙なく決めて、僕を出迎えたのだから、不意を突かれてドギマギしてしまった。それにしても不思議なことには、この家には彼女の夫、つまり沙也加ちゃんのパパの気配がいつだって全くないんだな。結局、僕は最後まで彼にはお目にかかる機会がないままで終わってしまった。
彼女と目が合うと、僕は、なんとか”今晩は“と挨拶をやり切った。法子さんは‟今日、なんだか暑いわね。ご苦労様”と首をかしげて笑うと、踊るかのように身を翻して、僕を沙也加ちゃんの部屋まで案内し、ドア越しに“沙也加、先生よ”と娘に声をかけた。法子さんは沙也加ちゃんの返事を待つわけでもなく、“よろしく頼むわね”とだけ言って、そのまま居間のほうに戻っていった。この人の後ろ姿はいつだって、この上なく優雅なんだ。
-2-
部屋に入ると、ママと同じような華奢で、やはりロングヘアだけど、こちらはまだお下げ髪にした沙也加ちゃんはポツンと机に向かって腰かけていた。法子ママの声も聞こえていたろうし、ドアが開く気配も察していたに違いないのだけど、向こうを向いたままこちらを振り向くこともしない。なにやら机の上のソニーの赤いミニラジカセをいじっていて、そこから田原俊彦の能天気な笑い声が音楽とともに流れ、フリルのついたブルーに小さな黄色水玉模様の上着がリズムに合わせて揺れている。机の上には歌謡曲だけでなく、マイケルのオフ・ザ・ウオールとかビリー・ジョエルなどの洋楽のカセットがいくつもとっちらかっていた。
”こんばんは、沙也加ちゃん、勉強の時間だ”と声をかけると、彼女は僕の方をほんの一瞬見返しただけで、再びラジカセに目線を落とし、少し間を置いてから、やっと観念したようにそれを止めてふと言った。
“先生、私、勉強なんかしたくないな”
沙也加ちゃんは頭の良い、というかとてもカンの良く回る子だ。その気にさえなれば、勉強だって決してできない子ではないだろう。ただ、それを法子ママが命じるように素直に勉強の方にむけることができないんだな。だから彼女との会話はいつもこんなやり取りからしか始められない。僕はショルダーバッグを下ろし、その中から参考書を取り出しながら尋ねた。
“今聞いていたのは、トシちゃんかい?“
“わかる?ブギ浮ぎI love youよ。面白いでしょ“
カッコいいとか、素敵とかいう子はきっといくらでいるだろう。でも”面白い“という11歳の娘って珍しくないだろうか?そして、沙也加ちゃんの表情にやっとこの年頃の子に相応しい笑いが戻った。
“そうだ、昨日、聖子ちゃんの新曲が発表されたの。ラジオからの録音だけど聞きたい?先生、聖子ちゃんなら好きだっていってたじゃない“
沙也加ちゃんは僕の返事も待たずに、別のカセットテープを手に取ると、それをセットしてスイッチを押した。
ラジカセから、ハープのアルペジオが流れると、そのまますぐに贅沢といっていいほど豊かなストリングスがフルートと絡まった前奏が続き、あっという間に室温と湿度を下げた。そこに今までの聖子からは聞いたことのないような濡れた歌声が乗った。
“かぁぜぇったちぬぅ~、いぃまぁゎあ あきぃ”
その声の流れた瞬間、東京の住宅街にある小部屋はさっぱりと消え去った。目の前には風に揺れる白樺林が広かり、振り向けば、そこには初秋の柔らかな日差しの下にうっすらと色づき始めた山並みからなる地平線が視界の届くまで彼方に拡がっていた。そんな景色の中で、聖子は別れの哀しみを、手垢のついた”さよなら”とではなく、もっと透明にSayonara, Sayonaraと歌っていた。恋人?あるいは兄弟だろうか?どちらとも決めつけることもできない、誰とも言い難い、だけど大切な人。その人との永遠の別れを表すSayonaraの声は切なく、同時にどこまでも爽やかだけど、朝露のように儚くもあった。聖子が声を上げると世界中の胸がかきむしられるのだ。
沙也加ちゃんは、今度はしっかり僕の目を見つめて訊いてきた。
“先生、どう、気に入った?”
-3-
こんな風なピントが合っているのかも判然としない、妙なやりとりを繰り返しながら、その後も僕は沙也加ちゃんの家に通い続けていた。
彼女のやる気のなさに手を焼き、いささか辟易としながら。法子さんは、そんな僕のくそ真面目な熱心さを大いに評価してくれたらしく、時にはお茶だけでなく、当時の僕には手に入れられるはずのなかった高級洋菓子、あるいは熱い肉がたっぷりとつまったサンドイッチなどの軽食を差し入れてくれた。
沙也加ちゃんは勉強の間こそ仏頂面でいかにも心ここにあらず、という表情だったけれども、彼女が今、夢中になっているアイドル歌手たちやその音楽の話になると、それまでの茫洋と攫みどころのない表情はさっと消え失せ、眼を輝かせて饒舌になった。
そして、彼女が、当時、最も熱心に憧れていたのは、もちろん松田聖子だった。一日も早く中学生になって、その時は今のストレートなお下げを聖子ちゃんのようなショートにしてしまいたいというのが彼女の切なる願いだった。
‟ママが、私が小学生だからって自由にさせてくれないのよ”
その時、既に聖子はかの有名な聖子カットをばっさりと切って、ショートにしてしまっていたのだ。
このようなことを書くと沙也加ちゃんは、その当時、どこにでもいた一般的な11才の女の子のひとりであるように思われるかもしれない。もちろん、そんな一面を持っていたことも事実だったけど、彼女にはそれだけでない、年不相応に醒めたところのあり、時として人をドキリとさせる観察眼を垣間見せるのだった。勉強の合間の息抜きに、聖子の新曲、赤いスイートピーを二人で聞いていた時だ。沙也加ちゃんはふと独り言のように漏らした。
“聖子ちゃんって不思議な人よ。絶対にこの歌の中の子のような子じゃない。ただ、みんなはそんな人だと思いたがっているだけ。“
-4-
年も替わり、また新しい春と夏が巡り去ろうとした頃、個人授業を終えた帰り際、法子さんが“ちょっとお願いがあるのだけど”と出し抜けに声をかけてきた。
彼女は僕を居間に招き入れて、ソファに座らせ、法子さん自身も僕の真正面に腰を据え、心持ち首をかしげて、ゆったりと話し出した。
この日の法子さんは前髪を下ろして、やはりメイクもノンスリーブの黒い上着もきっちりと決めていた。彼女の白くて長い指にはうっすらとしたピンクのネイルが光っている。法子さんが話をする時、顔をわずかにうつむき加減にして、上目使いのような角度で相手の目を、その大きな瞳で引きずり込むかのように覗き込む。そして、言葉のワンフレーズ毎に僅かな間を置きながら、声を心持ち掠らせ、目線を合わせたと思うと、外したりしながら言葉というより目で話すのだ。そこに、法子さんの言ったことには決して逆らうことは許さないという決然とした意志を込めながら。
”実は娘が松田聖子のコンサートに行きたがっているの。一人では出すにはまだ早いし、私はちょっと立て込んでいて予定がたたないの。でも私にはXXさんくらいしか頼りに出来る心当たりはないのね。あなたなら安心できるし、チケット代と食事代、日当も出すから、娘の付き添い頼めないかしら?”
僕は、突然の突飛な提案に驚いてしまった。だって家庭教師とはいえ、二十歳そこそこのあかの他人の、しかも男に12才の娘のエスコートを頼むなんてあまり普通とは言えないだろう?でも、すぐさま、これはピンと来た、あの娘が図ったんだって。
沙也加ちゃんには法子さんのような、一目見るだけで人を石に変えてしまうというメデューサの魔力はない。それは彼女がまだ幼いからかもしれないし、たとえ親子であっても、同じものを持てるわけではないという、この世の摂理から来る限界なのかもしれない。その代わり、沙也加ちゃんには策略があり、プランを立てることができる。そして、沙也加ちゃんは法子さんを見抜いていた。法子さんには世間的な常識に囚われない、というよりそういったことに疎い浮世離れしたところがあり、その上、彼女の全ての判断基準は彼女自身のゆるぎないカンに基づいていた。そして、僕はその彼女のカンというお眼鏡に‟忠実な護衛“として叶っていたというわけだ。
もちろん、僕としても、この提案は申し分もないものだった。あの”風立ちぬ“を聴かせてもらって以来、僕も沙也加ちゃんに負けないくらい、聖子に夢中になっていたからだ。沙也加ちゃんはもちろん、それもよく承知していた。
”申し訳ないけれど、いいかしら?”
法子さんはそのダイヤモンドの瞳で見つめられたら、一体、世界中の誰がその申し出を断れたろう?
-5-
コンサートの当日、僕は沙也加ちゃんと会場の最寄りの駅の改札口を出たところで待ち合わせることにした。法子さんからは、役目は”12才なのだから、本当によろしくね“とよくよく念を押されてていて、本来なら自宅から一緒について行かなくてはいけなかったのだが、僕にもその日は色々と他にもしなくてはならないことが一杯あったのだ。沙也加ちゃんに電話で事情を話すと、心得たもので、”わかったわ、先生。”と一言いっただけで、特に残念そうな様子を感じさせることもなかった。
ジーンズ以外にはたったひとつしか持っていないグレーのスラックスを履き、特に気に入っていた丸首のニットを着て家を出た後、ふとホールデン風の赤いハンチングを以前、買っていたことを思い出した。相手は12才だし、デートではなくて護衛なのだ、その上、今まで散々、洒落っ気とは無縁な格好で沙也加ちゃんと逢っていたのだ。今さら何を格好つけているんだ、とも思ったのだけど、でも今日くらい少しは格好をつけないと、彼女の方が可哀想ではないか、そんな風に思えて、結局、家に戻ることにした。
ところが肝心のハンチング帽がなかなか見つからない。結局、待ち合わせの駅に到着した時には、15分以上遅れてしまっていた。慌てて、ショルダーバッグの中の例のハンチング帽を取り出すのも忘れたまま電車を飛び出し、小走りで改札を出ると、そこにはボートハウスの青い文字ロゴの入った白いトレーナーとグレーのロングスカート、赤いソックスで、同じような赤いポシェットを首からかけた沙也加ちゃんが既に待っていた。いつものストレートの髪にはブローがかかっている。
僕はこの時、沙也加ちゃんが去年よりずっと大人っぽくなっていたことに初めて気づいた。そして、自分の胸の時計がチクタク急ぎ足になっていたことに驚いていた。
(出典:『松田聖子写真集 聖子ひとりじめ』CBSソニー出版/1981年)
沙也加ちゃんはすぐに僕に気づくと、手を振ってにっこりと微笑んだ。
“ごめん、少し遅れちゃったね”
とうに成人をしている青年が、もはや子供とばかりは言っていられない、といって大人にはまだ距離のある微妙な年齢の可愛い女の子と連れ立って歩くるというのは、ママの公認とはいえ、ばつの悪さと照れを感じてしまうものだ。照れ隠しに、笑いかけると、沙也加ちゃんは優しくはにかみながら応える。
“先生、気にしないで。私も今さっき、来たばかりだし“
遅れたとはいっても、コンサート開場までにもまだ一時間以上もたっぷりある時刻だ。
“喫茶店で少し休もう。遅れたお詫びだ。何か飲もうか?軽く食べてもいいよ“
彼女が“うん”とコクリと頷くので、僕らは会場の近くの喫茶店に入った。窓から覗く会場の入口付近には、開場にはまだ間があるというのに既に行列ができていて、関係者らしい人だかりとともにごった返している。
僕らはそんな様子を眺めながら、自分用にアイスココアと彼女のためにフルーツパフェを注文した。外に見える看板にはまだショートになる前の白いドレスに身を包んだ聖子カットの聖子のポスターが貼られて、僕らに笑いかけていた。
“先生、ママの申し出、驚いたでしょう?”
沙也加ちゃんがクリームを小さなスプーンで控えめに掬い取りながら尋ねてきた。
僕は軽く苦笑いをして返事をする。
“でも、それ、君がママにした提案だろう。ありがとう。正直に言って感謝しているんだ。ただ、初デートの相手が僕じゃあ、君が少し可哀そうだけど“
余裕を見せたつもりだったのだが、今度は沙也加ちゃんが苦笑いをしている。
“私はただママに助け船を出してあげただけ。それに先生まで巻き込んじゃって悪い事しちゃったと思っているの“
“??”
“ママね、パパには今日の聖子ちゃんのコンサート、ママが一緒について行くということにしているの。先生がパパに会うことはまずないと思うけど、そんなことになっちゃったら、このことは秘密よ”と悪戯っぽく微笑んだ。
”ごめん、ちょっと意味がよく分からないのだけど…“
“先生、ニブいわよ。きっと恋人なんていないでしょ、それじゃあ“
“??”
沙也加ちゃんは笑いを噛みころしながら、もう一度、クリームを一匙掬って口に入れた。そして、それを味わうように一息置くと、僕の目を覗き込んで続けた。
“ママは今、誰かと逢っているの。パパにそれがばれると都合の悪い人とね。”
と、それまで、屈託なく笑っていた沙也加ちゃんの表情が一瞬、強ばったように見えた。そして僕から視線を外して、外の聖子のポスターを眺めながら言った。
“でも、私、そんなこと気にしない。あの人はあの人で自由に好きにしたらいいのよ。
僕はどのように反応していいのかわからず、ただ黙っている以外なかった。
“ママとパパはもう2年くらい前からほとんど一緒に暮らしていないし、そのくせ今はまだ夫婦の格好だけはつけなくちゃならないと二人とも思い込んでいるの。バカみたい。
だらしなく狼狽えるのを隠すのに精いっぱいの僕にも助け舟をだすかのように、沙也加ちゃんは再び僕の方を向き直すと、大丈夫よ、とでも言うかのように優しく笑って、だけどキッパリと言った。
“先生、でも誤解しちゃだめよ。私、別にママやパパが嫌いなわけじゃないのだから。良いところだって一杯ある。それにあの人たち、あの人たちなりに私のことを大切にしてくれているし。”
彼女の表情の中に、十年後の彼女の顔がふと浮かんだように思えた。それは法子さんそのものだった。
“それと、先生、私からもう一つお願いがあるの。先生の今日のチケット、こっちのものと取り換えて。”
沙也加ちゃんはもう一枚のチケットを真っ赤なポーチから取り出した。
“実はね、私、今日のコンサートに一緒に行く約束をしているボーイフレンドがいるの。これが彼のチケット。私たちの席とは離れちゃっているので、先生の席と取り換えてもらいたいの”
沙也加ちゃんの少しばかりはにかんだ表情はいつの間にか、小学生の女の子のものに戻っていたけど、僕を覗く瞳は法子さんと同じダイヤモンドだった。
やれやれだ。僕は観念して、自分のチケットをショルダーバッグから取り出した。そして、ボーイフレンドと何か食べる必要もあるだろう、と言ってチケットと一緒に三千円を彼女に手渡し、代わりに彼女からもう一枚のチケットを受け取った。ただ僕には法子さんと約束した最低限の護衛の義務がある。チケットどころか交通費、食費として小遣いまで渡された。だから、コンサートが終わった後の8時半に駅の出口のところで待っている、家までは法子ママとの約束通りに送らせて欲しい、そんなことを言うと、沙也加ちゃんはあっさりとOKした。そして、すっと立ち上がったと思うと、僕の頬に本当に軽い、そよ風のようなキスをしたかと思うと、彼と落ち合うために、つむじ風のように喫茶店を飛び出していった。10カラットの微笑みを置き残して。
”あ~ぁ”。僕は思わず大きくため息をつくと、少々、苦いココアを一口、飲み込んだ。そして会計を済ますと、例のハンチングを取り出し、顔を隠すかのように深く被って外に出た。外では聖子の新曲が大音量でラジカセから流れている。新曲の”秘密の花園“だ。ふと気が付くと僕もこの曲を一緒に口ずさんでいた。
“月灯かり、青い岬に、ママの目をぬすんできたわ・・・“
-6-
会場に入って席につくと、ここに来た事を一瞬、後悔したね。だって周りは高校生か中学生たちばっかりで、特に男の子なんかみんなで“セイコーッ”てあらん限りの声で叫んでいるわけだ。そもそも僕はアイドル歌手のコンサートなどそれまで行ったこともなかったんで、面食らっちゃったんだな。しかも、僕はきっと今日来た観客の中で、きっとベスト20に入るぐらいの年寄りの観客だったに違いない。
もっともそんな観客の大多数の彼ら、彼女らも、実際には大した年の差があるわけじゃないから、今じゃ同じオヤジ・オバさんなんだろうけど、その時には、その僅かな差がまるで地球と冥王星の距離のように思えたな。仕方ないので、僕は今度こそハンチングを取り出して頭にかぶった。ひさしでできるだけ深く目の前を覆い、座席に深く座り込み、そして腕組みをして、寝たふりのまま、開演を待った。間もなくやっと会えるはず聖子も何か遠くの別世界の人のように思えてきたし、つまらないことばかり頭に浮かんできそうだったんで、とにかく何も考えないようにしていたわけだ。
暫くするとようやく会場のライトが落ちた。ざわついた会場が声を潜めた、と言いたいところだが、それでも一部の親衛隊のリーダーなんだろうか、大声で聖子の名を叫ぶ声は決して止むことはない。
やがてドラムがまずリズムをたたき出した。コーラスが“へロー、グッデイ・サンシャーイン”と入り、そのフレーズを繰り返すうちにベースやキーボード、管楽器も加わり、音がどんどん厚みを増していく。そして、カーテンには小さな顔と長い首、そして細い華奢な肩の輪郭と、腰から丸くキノコのように膨らんだロングドレスの陰がくっきりと映り、その影がリズムをとって踊り出した。遂に観客をじらしていたカーテンの幕が上がると、そこには確かに満面の笑みを浮かべるのピンクのロングドレスに身を包んだ松田聖子がスポットライトに照らされていた。
会場から一斉に起こる”セイコーッ”という野太い叫び声、そして聖子ちゃ~ん、という少女たちの歓声に包まれ、歌い声が会場に響き渡り始める。幕が上がり切って、ステップを踏み始めた時、ピンクのキートン帽子が前にずれ落ちかかった。聖子は、慌てず、ちょっぴり苦笑いを浮かべてそれを手で押さえると、そのまま重心を前がかりにしてズンズンと今にも足音をたてるかの進み出ながら、歌を続けた。次の瞬間にはステージ上を上手、そして下手とサイドステップで動きまわり、手をひとりひとりのファンに向かって振りながら。
聖子はピンクのスクーターを歌い終えたが、バックバンド、コンソレーションの演奏は、止まることなく、そのまま次の曲が続く。親衛隊はホイッスルやリズムの外れた手拍子で煽るけれども、この曲での聖子は動き回ることも控え、マイクを両手で握りしめて、肩でリズムを取りながら、切々と歌い上げたのはSailingだ。その明るく、だけど心をかきむしるような可憐な声は、聖子の体全身を共振させ、大気を震わし、会場をレモン風味のマシュマロのように包み込んだ。そんな聖子が声を上げると世界がほほ笑み返した。
“今晩は。松田聖子です!”
聖子はその後、何万回と繰り返されることになるこの挨拶を、しっかりと背筋を伸ばし、深々としたお辞儀と一緒に行った。喋り方は落ち着いて、テレビで見るベビーフェイスの年齢より子供っぽいところは感じられず、むしろやんちゃできかん坊どもを手抜かりなく統率するしっかり者の幼稚園の先生を思わせた。
そう、少女のように見えるこの二十歳になった、僕とほぼ同い年のこのひとは、実際には年相応の、いや、もしかしたら年齢以上に精神的には成熟した大人の女性であるのかもしれない。ただ、歌っている時の聖子は大人でも子供でもない、ただ王道アイドルの化身だった。それは松田聖子の本体であるはずの九州出身のあの女性でさえなく、それ以上の特別な何かなのだ。
テレビの中では運動能力が高いとも思えなかった少女が、今やステージを縦横無尽に動き回るだけでなく、素早いシャープな動きで、リズムに合わせてポーズをフィルインで決めたかと思うと、重力から解き放たれたかのように軽々と身を翻しているのだ。さほど大きいとは言えない体をゴム毬のように弾ませ、二千人の聴衆‐えっ、たった?誤解しないで欲しい、今と違って、聖子は全国隅々の地方都市のけっして大きいとはいえないコンサートホールまでマメに回っていた。ほとんどの週末の土日を使って、しかも一日二回公演だ。なにもプレミアムシートでなくとも、聖子は豆粒ではなく、その愛らしい口元も黒い目もはっきりと見わけのつく至近距離にいた。バンドだけでダンサーもいないまま、二千人の視線をたった一人の歌だけで受け止めていたのだ、今から見ればまるで学芸会のようなちゃちな舞台装置だけをバックに。
聖子は、時にリラックスしたトークを織り交ぜ、幼稚園の先生に戻るかと思うと、また妖精アイドルとして誰もが知る彼女のヒットシングルを歌い綴った。そして、コンサートでしか聴くことのできないアルバム曲も、特にアルバム”風立ちぬ”とPineappleから随分と取り上げた。
僕はいつの間にか邪魔なハンチング帽をポケットにしまい込み、前の席に体を持たせかけ、首から顔を抜き取らんばかりの勢いで、夢中でステージ上の聖子の表情ひとつひとつを目で追い、声の一音一音を死で捉まえようとした。
ファイナルはあのOnly my Love。終幕の時、カーテンが降りようとすると、聖子は深々と挨拶をした後、僕等、観客に向けて、懸命にバイバイの手を振った。最初は背筋を伸ばして、やがてカーテンが自分より低い位置にまでくると、腰を屈め、さらにカーテンが低くなると遂に聖子はしゃがみ込み、遂には顔を床にこすりつけるような姿勢となった。それでもカーテンの裾越しに伸ばされた腕は、カーテンが完全に落ちきるまで手を振り続けるのを止めなかった。あの頃、ステージからも見えていたに違いない僕たちの顔は聖子にはどのように映ったのだろう。
-7-
駅で沙也加ちゃん待っていると、今度は彼女が約束の時間に15分ほど遅れた。もちろん彼女は謝ってきたけれど、最初に遅れたのは僕の方なのだ。文句など言えるはずがない。今さっき、別れただろうボーイフレンドのことも一切触れないことにした。僕も君と一緒に共犯になってやるさ。
ただ一言、“どうだった?”と訊くと、“もちろん”とだけ沙也加ちゃんは笑って応えた。そしてへぇーとでも言いたげな意外そうな声で“先生、その赤い帽子、どうしたの?”と尋ね返してきた。君のために準備したんだけど、からぶっちゃった、と言いかけたが、これはどう考えても野暮だ。
僕は“いちご畑のホールデンのふりさ。”とだけ、短く答え、目配せをすると、沙也加ちゃんは、ちょっと怪訝そうな表情をみせたが、特にそれ以上はつっこむこともなく、クスリと小さく笑っていた。思いもかけず、何かの秘密を探り出してしまった探偵のように。
僕たちは電車を待つ間も、車内でもほとんど話さなかった。車内は混んでいて、座ることも出来ない。いくつかの駅を停車すると座席が空いたのが見えたので“座るかい?”と尋ねたが、彼女は首を振った。といって、別に彼女が不機嫌だったわけでは全くない。沙也加ちゃんは静かに扉の窓から外を眺めていたけど、穏やかな表情で、時々、微笑んでいるようにさえみえた。コンサートの余韻を楽しんでいたのかもしれない。ポケットから取り出したクールミントのガムを取り出し、彼女がそれを笑って受け取ると、自分でもそれを口に入れた。沙也加ちゃんが見つめる窓の先には、すっかり暗くなった夜空の下に街明かりが銀河のように光っている。
やがて、彼女が本当に小さな声で、誰にもわからないようにリズムを取りながら何かを口ずさんでいるのがわかった。よく耳を澄ますと、それは聖子の“いちご畑でつかまえて”だった。
“好きな人出来たら、最初はにげるものよ、そーおう、教わったママの恋の手ほどき・・・”
僕の脳裏には、つい一時間にも満たない前の、この歌を歌う聖子の様子が鮮やかに浮かんだ。聖子は赤いミニドレスで、その後、誰もが聖子といえば真っ先に思い浮かべる、だけど当時の僕らにはまだまだ目新しかった、あの甘く擽るような声で歌っていた。笑顔を弾けさせたと思うと、はにかみ、意味深な困り顔をしたかと思うと、悪戯っぽく誘い込むようにと、その表情を五秒に一回、猫の目のようにくるくる変えながら、そして、ひらひらと蝶のように舞いながら。
“ビタン、ビタン、ビドゥビドゥビ・ダン・ダン、ビタン、ビタン、ビドゥビドゥダァ”
聖子が声をあげると、世界は軽やかに躍動した。
そして、目の前の現実の沙也加ちゃんが同じスキャットを、微かな声で聖子の声に重ねていた。それは、きっとこの世界が望みうる最も精妙で美しい音のハーモニーでありタペストリーであるに違いない。この瞬間がこのまま永遠のもっと果て、海の果てまで続いてくれば・・・それこそが僕が追い求め続けていくものだろう。
“ビタン、ビタン、ビドゥビドゥビ・ダン、ビタン、ビタン、ビドゥビドゥダァ”
(了)
--------
(たいむましんアイドル担当Tより)
この文章がJ.D.サリンジャーの名著『ライ麦畑でつかまえて』のパロディであることは、ご想像の通りです。ちなみに”ホールデン”とは主人公”ホールデン・コールフィールド”からです。他にも文中には歌詞の引用だったり、”法子さん”の服装は”哀しみのボート”のPVからだったりと、仕掛けがあります。それも含めて是非楽しんで頂ければ幸いです。
---------
(参考文献)
『ライ麦畑でつかまえて』(J.D.サリンジャー著/野崎孝訳/白水社)
『松田聖子写真集 聖子ひとりじめ』CBSソニー出版)
※写真3枚目は1983年の「アン・ドゥ・トロワ」コンサートポスターより。
1960年生まれ。
様々な音との出会いを求めて世界を彷徨い続けていますが、ふとした拍子に立ち戻るのは、ジョアン・ジルベルトと松田聖子、そしてエリック・ドルフィーの音の世界。聖ジュネで示された方法論を応用して聖子を理解し、語り尽くすのが夢。
プロフィール写真はJose Antonio Mendezの「ESCRIBE SOLO PARA ENAMORADOS/フィーリンの真実」レコードジャケットより。
Twitter ID:@bossacoubana

記事一覧はこちら