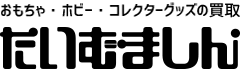Seiko Jazz 0(ゼロ)<中編> ~幻の未発表曲”One of these days” (この、いつの日か)~
(上編より続く)
5.”One of these days” と”Reflections in D”
ということでもう一度、この曲””One of these days”とデュークの原曲”Reflections in D”を聴き比べて欲しい。何かお気づきにならないだろうか?
そう、”One of these days”のピアノと、デュークのオリジナル・ピアノ演奏、あまりにも似すぎている!
実はこの2曲のテンポも演奏時間もほぼ、というより全く同じなのだ。出だしやエンディングのピアノのコーダも同じ。しかもピアノの演奏が主旋律を奏で、聖子のヴォーカルとユニゾンになるという通常の伴奏では考えられない編曲。聖子コミュニティに集う仲間たちとも検討しあった結果、導きだされた結論は、ただひとつ、このピアノ演奏は同一のものであるということだ。
もちろん1953年の録音と2011年の録音では音質も大分違うし、演奏のキーも違っている。そもそも、聖子の生まれる前に既に録音されていたピアノ演奏のキーが歌と合うわけはない。そこで、デューク自身のピアノ演奏にデジタル修正をかけた上で、ヴィブラフォンやフルート、ストリングスを控えめに乗せ、最後に聖子のヴォーカルを乗せたものこそ、Mr.Q版”reflection in D”つまり”One of these days”なのである。
Mr.Qは聖子に、ただ単にデュークの曲を歌わせるだけでは終わらなかった。聖子のあの声にデューク自身のピアノを溶け合わせることで、これまでにない極上のQ流カクテルを作り上げたかったのだ。このことを聖子も我ら聖子ファンも誇りに思っていい。
実は”Reflection in D”にはトニー・ベネットの“Refrections”と題されたヴォーカルヴァージョンがある。トニー・ベネットは近年ではあのレディ・ガガとも共演したことで知られるアメリカの大ベテラン大御所歌手だが、彼のヴァージョンと”One of these days”では曲は同じでも、その歌詞は全く別物である。→https://www.youtube.com/watch?v=NGDuIRtnDNg
さて、みなさん、トニー・ベネットと聖子のヴァージョン、どちらが良いと思われるだろうか?私はトニー・ベネットのやたら大声を張り上げる歌い方が、何を歌ってもガサツに思えてあまり好きになれなないのだが、その上、歌詞の中身もトニー版は「昔、昔、私は心を捧げて、人生はとても甘く見えたものだが、それはダメになって、でもあなたが愛してくれて、世界は明るい”」みたいなやたら単純なもの。デュークの書いた繊細でメランコリックなメロディーさを活かせているとはまるで思えない。
一方でMr.Qはこの歌詞に満足せず、聖子に歌わせるに際し、わざわざ全く別の歌詞まで準備した。
One of these days “いつか、そのうち”
is one touch away from “それは遠いあの幾夜の”
one of those nights “ひとつからの手触り”
when all lights go dim “灯がすべてほの暗くなり、
and moonlight, one night ”月明かりの中で、ある夜・・・“
通り一遍の解釈を拒否するような意味深で謎めいた、しかし繊細な歌詞で、演奏のみならず、歌詞まで含めてここまで舞台を演出したMr.Qのデュークへの思い、聖子にかけた情熱、凄まじいまでのものではないか。一体、いつから聖子とMr.Qの関係は始まり、どのように深まっていったのだろうか?
6.聖子とクインシー
聖子はデビュー翌年の81年の「Nice Summerコンサート」で70年代クインシーの代表曲、”愛のコリーダ”を歌っている。この時のパフォーマンスはNHKのレッツゴーヤングの特集「聖子、夏を行く」で取り上げられ、You Tube等でも見れるので知っている方も多いだろう。僕ら聖子ファンには、たどたどしいながら一生懸命歌い踊る聖子がひたすら健気で可愛い!という代物だが、音楽的には、当時の聖子、まだまだソウル‐R&B的なノリを身につけるには至っておらず、いかにも“私、洋楽お勉強中、未熟だけど頑張るからよろしくね♡”というレヴェルだ(苦笑)。
この頃は、この曲の収録されたクインシー自身のリーダーアルバムである『The dude』、そしてあのマイケル・ジャクソンとクインシーのコンビの第一弾『Off the wall』が大ヒットした直後で、きっとデビューまではまともに洋楽など聞いたこともなかったであろう聖子もプロ歌手としての義務感もあって、さかんにこうした大ヒット洋楽アルバムを聞き始めていたのだろう。
確か81年だか82年ごろの雑誌『明星』だったか、聖子の愛聴盤のアルバムということで『Off the wall』やクインシーのこのアルバムが取り上げられていた記憶がある。だから、聖子から見ればクインシーは洋楽に本格的に目覚めた頃からの憧れの存在、後にアメリカ進出を目指すころになれば、どうしても協力を得たい相手だったことは間違いない。でもクインシーから見た聖子はどうだったのだろう?
(1981年。Nice Summerコンサートのパンフレット。この写真のみ編集者T提供。)
7.聖子への“謝辞”?~クインシーのバック・オン・ザ・ブロック~
実はクインシーが聖子知ったのは案外と古く、なんと彼の89年のアルバム『Back on the block』の最後の献辞には、このアルバムに参加したチャカ・カーン、スティービー・ワンダー、マイルズ・デヴィスやサラ・ヴォ―ンといった錚々たる高名なミュージシャンやクインシーの家族や友人たちに交じって、Seiko Matsudaの名前もしっかりと(でも実はかなりひっそり奥ゆかしくだけど)記されているのである。1989年といえば、聖子のアメリカデビュー盤『Seiko』の発売前である。
(『Back on the block』ジャケット写真より)
一般的に音楽家に限らずアーチストには、自分の才能を恃むあまり、ジコチューで付き合うには相当な困ったチャンというタイプが多いのだが、クインシーは全くそれとは別タイプ。音楽の才能も一級品なのだろうが、一方でとても社交的で如才なく、他人との才能の交わりの中で自他ともにインスパイアし、それを組み合わせることで、自分も大いに楽しみながら音楽を作っていく、そんなタイプの音楽家らしい(聖子ちゃん、クインシーのそうした美点はよく研究して見習うようにね!)。
彼は音楽のジャンルにこだわらないのはもちろん、音楽以外のフィールドの人間とも人種や国籍に囚われることなく、やたら広大な交遊関係を築いているので、そのネットワークの中に、バブル崩壊前の絶好調であったソニーの大プッシュを受けた聖子が入ってきても何ら不思議はないのだが、それにしても、オリジナルアルバムの献辞に片隅とはいえ、その名前が入るとは、一体、何があったのだろうか?
『Back on the block』はクインシーらしい80年代マイケル風ポップR&Bとブラコンの王道をゆく楽曲を中心に、当時台頭していたラップと、クインシーの音楽的バックグランドであるジャズのフレイバーを強く振り掛けたもので、残念ながらそこに当時の聖子が入る余地は見当たらない。
聖子全盛期の80年代聖子ミュージックには、クインシーのバックグランドであるジャズやR&Bのブラックな要素がほとんど見られないし、聖子自身の声質もヴォリューム豊かにこってり、という王道アメリカン・ブラックミュージックの世界とはかなり異質だ。とはいえ、クインシー、あの聖子の80年代の燦然たる傑作アルバム群を聞いたということはないだろうか?
結局、アメリカ発売は見送られたが、聖子初の英語アルバム『Sound of my heart』のプロデューサー、フィル・ラモーンは、クインシーとはかなり親しい間柄だ。彼から聖子の音楽的な情報が、流れて来ていたとしてもおかしくない。
(『Back on block』に掲載された献辞)
“彼女は独特のメロウな声の持ち主で、キーを外すことなく歌っていた。一人前のロックンローラーでもキーを外しているものは多い。私が彼女と契約を交わす気になったのはそれが理由だった。” (クインシー・ジョーンズ自伝より)
実は、ここでクインシーが触れているのは聖子のことではない。クインシーにとって初めての全米No.1ヒットとなった60年代の白人のアメリカンポップ歌手、レスリー・ゴーアについてだ。
マーキュリーで黒人初の副社長となったクインシーはたくさんの高品質なレコード(主にはジャズ)を60年代初期に制作したものの、どれも”売れない名盤“ばかりで、社内で追い詰められてしまった。結局、”ポップスのヒットを作るなんてたいしたことじゃない“と苦し紛れで吹いたのが運の尽き、”それならやってみせてくれよ“と社長に言われて、引くに引けなくなって手掛けることになったのがレスリーだった。
ただ、同時にクインシーは”単にヒット曲を作るためだけでは越えられない音楽的な一線がある“とも言っていて、ビジネスだけでは終わらない、彼の音楽的感性にひっかかったからこそのプロデュースだったとことを強調している。たとえ期近に音楽的な接点は見つけられなかったにせよ、日本から来た、アメリカ人には十代の少女にしか見えないこの歌手にクインシーが何らかの音楽的興味を感じたことは十分ありうることである。
もっとも聖子があの時、クインシーの関心を惹くことができたのは、音楽以外の要因だった可能性もある。思い当たるのは聖子とクインシー、人間的な相性が良いというか、要はウマがあったのではないか、ということだ。
クインシーは自他ともに認める大変な女たらしだが、実はたらすのは女性だけでなく、男も、老いも若きも、誰でも彼を知る人を惹きつけずにはいられない天性の人たらしであるらしい。そして人たらしという点では聖子も同じだ。そして聖子の人たらしの才は、あの時代、やたら酷いパッシングに曝された日本よりもアメリカでより自由闊達に発揮されていたように見える。それを〝たかが日本のアイドルがアメリカまでいって何をはしゃいでいやがる“、と嫌味の目でしか見れなかった当時の日本人の了見の狭さ…というのはまた別の問題だな。
8. 進まないコラボ
それでも、二人の実際の音楽共同作業はご存知の通り、容易に進まなかった。クインシーは興味の対照が次から次へと移り変わり、新しいプロジェクトが現れては消えていったし、その上、この頃のクインシーは音楽業界以外の分野にも積極的に進出していったからなおさらだったろう。それに聖子の方だって、90年代はアメリカと日本を股にかけ、クインシーに負けず劣らず忙しかったのだ。
ただ聖子は諦めなかった。90年代に入り聖子はブラコンというかR&Bに懸命に接近してゆく。クインシー自身と関係の深いマーキュリー(クインシーがかつてマーキュリーの副社長だったことは既に述べた通り)に移籍し、98年には聖子のキャリアの中で最もR&B的なアルバム『Was it the future』を作る。
アメリカ進出時の聖子のアルバムは決して評判が良いわけではないが、このアルバムは今聞き返すと、それほど悪い出来ではない。少なくとも90代からの2000年代の買ってはみたけれど、一回か二回聞いてあとはCD棚の肥やしと化してしまう、日本発売の聖子オリジナルアルバム群より遥かにきちんと作られているし、聖子の歌も気合が全く違う。全部とは言えないけど、少なくとも”Let’s talk about it”など、幾つかの曲はR&B的な文脈(じゃなくて音脈か?)の中に聖子の声がきちんと活かされている。これは聖子の“どう?私、ここまでできるのよ”というクインシーへの音楽ラブレターではないだろうか?
一方、クインシーの方も90年代にはいってから音楽の方向性が微妙に変わってきている。さすがのクインシーも還暦を迎え、その音楽活動はペースダウンを始め。もはや、それ以前のように遮二無二コンテンポラリーな音楽の最前線に立つのでなく、自己の音楽履歴を振り返るような回顧的な素材が多く取り上げらえるようになった。相変わらず、やたら豪華なゲストを迎えてはいるものの、派手でゴージャスな音作りは多少控えめとなり、より落ちつた出来になったのが90年代唯一の、そして今のところリーダーアルバムとしてはキャリア最後のアルバム『Q’s Jook Joint』だ。
注目すべき曲がふたつある。ひとつは新人女性歌手Tamiaに歌わせた”You put a move on my heart”であり、もうひとつが前述した”Do nothing till you hear from me”というデューク・エリントンの曲のカバーだ。
Tamiaは黒人歌手としては軽い声質で歌い方もR&B的なねっとりとしたノリは控えめのスムースな歌い方で、この曲ならあるいは聖子でも!と思えるものだし、エリントン曲のカバーでヴォーカルを取るのはなんとこれまた畑違いと思われかねないフィル・コリンズだ!ここではデュークのオリジナル(盲目の黒人歌手アル・ヒブラーがねっちりと歌う)とは全く毛色の違う歌手にリードを取らせ、原曲のアクの強さをほどよく脱色、手際よく現代のポップスにしている。
この方法論をさらに高度に洗練させたものが聖子の”One of these days”だ。だが、聖子とクインシーが具体的に音楽を作り出すにはさらに10年以上が必要だった。そして、この間の事情は今でも全く不明だ。
(下編に続く)
1960年生まれ。
様々な音との出会いを求めて世界を彷徨い続けていますが、ふとした拍子に立ち戻るのは、ジョアン・ジルベルトと松田聖子、そしてエリック・ドルフィーの音の世界。聖ジュネで示された方法論を応用して聖子を理解し、語り尽くすのが夢。
プロフィール写真はJose Antonio Mendezの「ESCRIBE SOLO PARA ENAMORADOS/フィーリンの真実」レコードジャケットより。
Twitter ID:@bossacoubana

記事一覧はこちら